【寄稿】個人プレー頼みからチームプレーに変わる「組織のOS」をつくるためにやったこと
AIリスク情報サービス「FASTALERT」やニュース速報アプリ「NewsDigest」などを展開する、株式会社JX通信社 代表取締役 米重 克洋さんからの寄稿記事をお届けします。
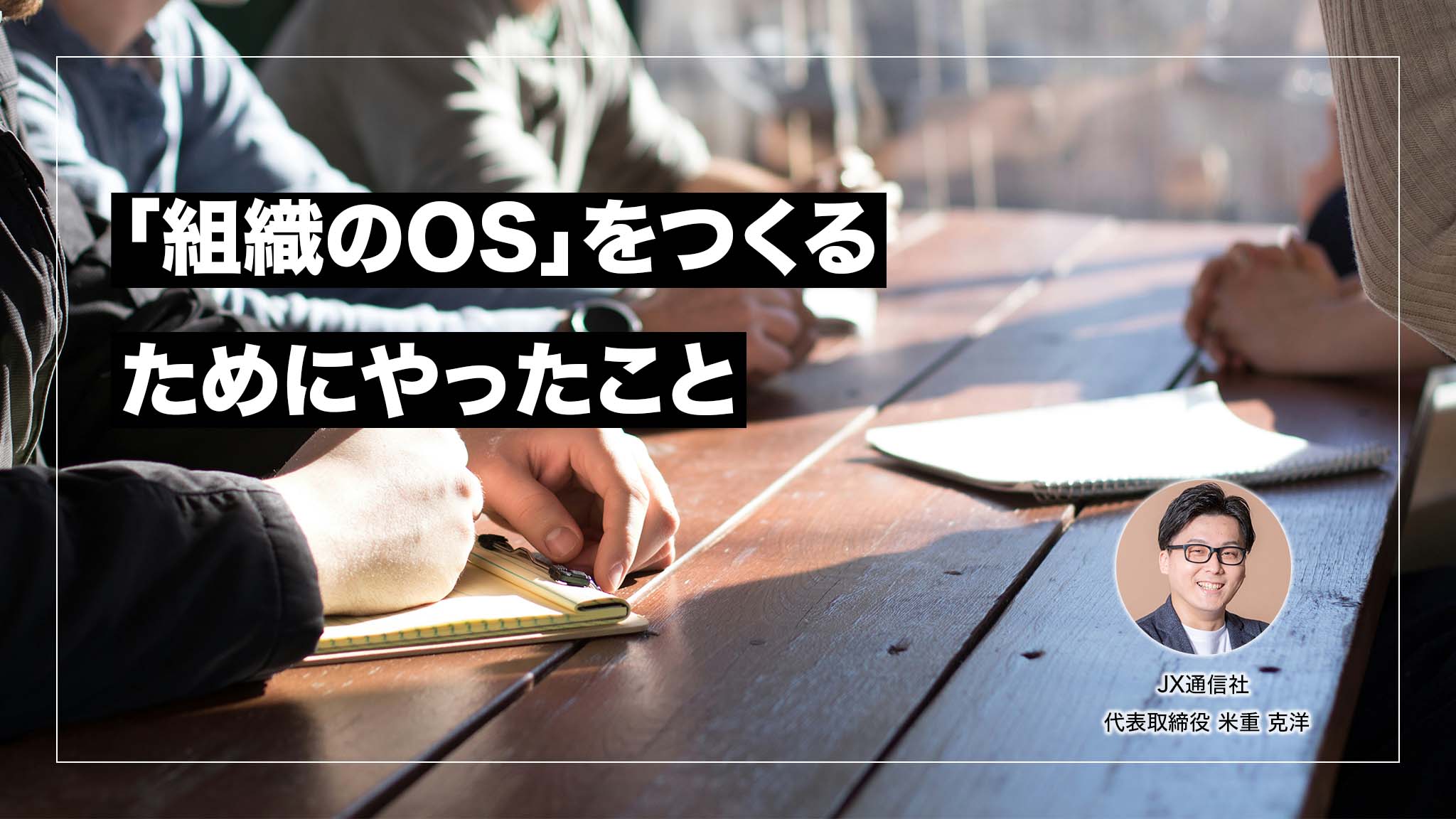
こんにちは、JX通信社の米重です。
JX通信社は「データインテリジェンスの力で、より豊かで安全な社会を創る」ことをミッションとする、報道ベンチャーです。「どこで、何が起きたのか」「皆はどう思っているのか」をデータで可視化できれば、世の中のぜんぶが分かる──。そんなコンセプトのもと、ビッグデータとテクノロジーを活かして、全国の報道機関や自治体、企業、一般消費者に価値ある情報をいち早く届けるべく、ニュース速報や世論調査の領域で事業に取り組んでいます。
私たちは3年ほど前に、スタートアップ特有の「組織の壁」に直面したことがあります。少人数だったころの属人的な仕事の進め方のまま組織が大きくなったため、チーム間の情報共有がうまくいかず、事業拡大のスピードにも大きな問題が生じてきてしまいました。
そんなとき、グローバル・ブレインの投資先スタートアップの事業支援を行う専門チーム「Value Up Team(VUT)」からサポートを受ける機会に恵まれます。
VUTは営業やマーケティングの戦略・実行支援、エンジニア採用の支援など具体的な事業課題の解決に伴走してくれるチームですが、彼らの貢献はそれだけに留まりません。私たちが今後さらに事業を拡大していってもしっかり対応できる「強い組織」になるための支援を受けることができました。
VUTの皆さんとの取り組みを通じて、良くも悪くもベンチャーらしいカオスな状態だったJX通信社に、健全な「組織のOS」がインストールされました。個人プレー頼みではなくチームプレーで仕事を進められるようになった結果、意思決定やPDCAのスピードも上がったと感じています。
この変化を通じて、私は組織のOSを整えるためには、以下の「5つのポイント」が重要だと考えました。
- 情報共有:会社の「共有知」を増やす
- 権限移譲:メンバーを信じて任せる
- 問題解決:皆で問題を解く
- 振り返り:「お客様」と「コト」に向かう
- マインド:全員がオープンマインドでいる
この記事では、私たちがVUTの皆さんの力を借りながら、どのようなことに取り組み、改善を進めていったのかをご紹介します。
1.会社の「共有知」を増やす
属人的だった組織を変えるためにVUTとまず取り組んだのが、メンバーが持つ知見を会社の「共有知」にする仕組みづくりです。
以前まで私たちの業務は、オーナーシップを持つ個々人が、部署もチームも関係なく社内に落ちているボールを拾っていくことで成り立っていました。これは端から見ると機動力があり、自由度の高い組織のように思えるかもしれませんが、実際のところは個々人への依存度が高く、リスクが多い状態だったと思います。「この人がいないと何もわからない」という業務がいくつもあり、個々人に過剰に負荷がかかったり、事業や組織拡大の妨げにもなったりしていました。
そこで取り組んだのが、経営チームもそれ以外のメンバーも皆がスムーズに議論し、よりよい意思決定とアクションにつなげられるよう、情報を整理・共有するカルチャーづくりです。
VUTからは議事録をはじめとするドキュメントの要諦や、非同期での適切な情報伝達を通じて共有知を増やし、事業を加速させるための具体的な改善提案を多くいただきました。いわば「情報共有」の仕組みと技術を組織全体にインストールする支援をしていただいたと思います。
これは単なる助言ではなく、実際の行動に直結するものです。たとえば、VUTの皆さんには社内の定例会議にも同席いただき、会議前のアジェンダ準備や議論のポイントの整理、ネクストアクションやオーナーの定義まで、メンバーと伴走して支援いただきました。まるでいちメンバーかのように深く入り込んで本質的な議論になるようサポートしていただいたことは、非常に印象に残っています。
こうした取り組みの結果、全社的にドキュメンテーションの力が徐々に向上していくのを体感しました。ここは、以前まで個としてはできていても、組織全体ではムラが大きかった点です。従来は部署や担当者によって会議のあり方がまちまちでしたが、いまではどんな会議であっても、開始前には必要な事項が書かれたドキュメントが、終了後には決定事項やネクストアクションが共有されるのが当たり前になっています。結果、各チームの状況やノウハウが会社の共有知として蓄積されるようになりました。
これによって、私たちにはある変化が起こります。それは意思決定の質の向上です。
弊社における過去のさまざまなコミュニケーションをつぶさに調べたところ、「あれはどうだっけ?」「これはどうなっているの?」といった担当者への状況確認に多くの時間を取られていたことがわかりました。本来、言語化された情報がドキュメントとして記録されていれば、必要ないやりとりです。
しかし情報のドキュメント化が以前より格段に徹底されたことで、いまでは社内のドキュメントを検索すれば多くの情報がすぐに見つかるようになっています。
こうした取り組みは、言葉にすれば実に簡単なことに聞こえるのですが、個々人の意識や能力だけで改善するものではありません。組織の文化として全社的に浸透させていくのは思った以上に難しいものです。
そうした点も含めて、VUTの皆さんに深く入ってサポートしていただいた結果、会議ではその場でしかできない本質的な議論に割ける時間が格段に増え、意思決定の質・スピードが確実に上がったと感じます。
2.メンバーを信じて任せる
情報共有の方法が改善されたのは、私たちにとって大きな変化でした。しかし、これだけでは属人化してしまった組織の状況を改善しきれません。より動きを加速させるためには、適切な「権限移譲」も大切です。この点でもVUTからは積極的にサポートしていただきました。
権限移譲において大切なのは、メンバーに達成してほしいゴールを「状態目標」で共有することだと思います。
状態目標とは「ありたい姿」のこと。チームの仲間には「こういう状態にしてほしい」という目標とその背景にある意図だけをしっかりと伝えて、そのやり方は任せるのが一番だといまは考えています。
私は元々、どちらかと言えば細かい性格です。業務プロセスの多くに介在して「あれをやってほしい、これをお願いします」と、やり方を細かく指示するタイプのマネジメントをしていたと思います。たとえばお客様に提案するための商談資料も1つずつ確認する、といった具合です。
しかし、こうしたスタイル一辺倒では、私1人に会社全体の細かな確認事項が一極集中してしまい、会社全体の進みが遅くなってしまいます。実際、私自身がボトルネックになってしまい、先ほどの例でいうと営業チームは修正がなされないまま古い資料を使って商談を続けざるを得ない、といった事態も発生してしまいました。
私と1on1を行ってくれたVUTのメンバーは、「メンバーを信じて任せて、米重さんは経営者にしかできない仕事をしましょう」と度々助言してくれました。私の時間の使い方を変えるために「この課題はXXさんに任せられる」「この話はXXチームに振ってもよいのでは」など、客観的な視点で業務の再配分にコメントいただいたこともあります。
自分を客観的に省みても、仕事の進め方や行動パターンを変えていくのは簡単なようでなかなか難易度が高いことだと思います。特に経営の立場では、マネジメントを「受けている」立場ではないので課題に気づく機会すら逸することも少なくありません。
投資家でありながら真の意味で「伴走」し、実態に即した助言や支援をしていただいたVUTのおかげで、自分のスタイルや組織の状況は大きく変わりました。かつて私や経営チームは、箸の上げ下ろしから細かくコメントし、同時に自分もいちプレイヤーとして動くスタイルでしたが、いまではチーム全体で状態目標を共有し、自律的にやり方を考え実行し、検証するまでを各メンバーに任せられるように大きく改善しています。
こうした権限移譲がさまざまな領域で進んだ結果、私が深く感じたのは「1人よりも5人、5人より10人、10人よりも100人の頭で考え、動いた方がアウトプットの質も量もよくなる」ということでした。
これも言葉にすれば実に当たり前のことです。営業で使う提案資料は、目の前の1人のお客様の顔や声、お悩みに毎日集中的に向き合っている営業メンバーが、自らの権限と責任のもとどんどんアップデートしていったほうが、より響くものになるに決まっています。
従来「自分でやった方が早い」「自分が細かく口出しした方が良い」というスタイル一辺倒だった私の中で、任せて皆でやった方が圧倒的に良くなる体験が増えてきました。具体的な例を挙げればキリがないくらいです。結果、私自身もさらに成長し、権限移譲を進めていく踏ん切りを徐々につけていくことができました。
ありたい姿やビジョンを示すのがCEOやマネージャーの最も重要な役割です。いわば、登りたい山を示すのがあるべき役割であり、それをせずに細かな登山ルートやスケジュールばかりを指示するべきではありません。VUTとの関わりを通してそのことを強く学びました。
3.皆で問題を解く
情報共有や権限移譲が全社に浸透し、JX通信社のできることが増えるにつれ、「問題解決」のスキルも向上していくことになります。
前述の通り、以前は私を含めた組織内の一部の人間が、非常に細かなレベルの行動計画を決めてしまっていました。
しかしいまでは、各チームから自然と「私たちは次に何をすべきか」と議論が起こります。各チームが権限移譲によって進め方を任せられているので、徹底的なドキュメンテーションのもと効率的に議論し、自律的に次のアクションを考え、決めて動けるようになってきました。
繰り返しになりますが、1人ですべての問題を解くより、50人なら50人、100人なら100人の頭で考えたほうが当然早く進みます。大量のトライアンドエラーが各所で行われるようになったことで事業のスピード感も変わってきました。この「皆で考える」習慣ができたのは組織の財産だと感じています。
各チームが自ら問題解決に挑むようになって、私自身の経営者像も変化していくのを感じました。
経営者は会社のすべての責任をとる必要があっても、すべての仕事をする必要はないのではないかと。
私は、経営者は戦略を実行可能な戦術レベルまで細かく決め込んで、チームに提示して引っ張っていくのが最も望ましい姿だと思い込んでいるところがありました。しかしそれでは、組織や業務の幅が広がるにつれてワークしなくなっていきます。
大きな組織で事業を成長させるためには、大量のトライアンドエラーとスピードが必要になります。そしてスピードを出すためにも、誰か1人ではなく「皆で考える」というシンプルなこだわりが重要です。
そのために経営者がすべきなのは、まずは登るべき山としての状態目標や、そこに至るための大きな戦略を描くこと。ここが基本で、それよりも細かなレベルであれば、あくまであるべき状態目標からズレてしまいそうになったときにだけ議論やフィードバックを通じて軌道修正すれば良い。それが経営者に必要な優先順位の考え方だといまは捉えています。これは私の中で大きな思考の変化でした。
4.「お客様」と「コト」に向かう
組織全体で事業の課題を克服していくためには、何かを実行した後の「振り返り」にも望ましいやり方があると思っています。
私だけでなく、経営チーム全体で、振り返りの議論の際に特に意識しているポイントは2つです。
1つは「お客様のため」という視点を忘れないことです。「お客様のため」や「顧客第一」「ユーザーファースト」といった言葉はどんな会社でも二言目には出てきそうなワードなので、時として飾り文句のようになってしまうこともあると思います。しかし、これは決して飾り文句に留めてはならない、振り返りの根幹にすべき大切な視点です。
企業では各チームが自分たちの視点で考えて施策を実行しようとすると、お互いの課題の認識や利害が一致しないケースも出てきます。そんなときには、メンバー間で他責的なコメントが出てしまう場面もあるかもしれません。
しかし、社内のどんな立場、役職、部署であれ「お客様の課題を解決する」のが事業に取り組む本来の目的です。このことは全員に共通するはずです。そこをふと忘れそうになったとき、それぞれの立場から何が「顧客第一」なのか、考え、議論する場を持つことが大事だと思います。
VUTと組織力向上に取り組む中でも「お客様に最適なものを早く届ける組織になる」ことは1つの目標に置いていました。基本的なことながら、決して忘れてはならない観点です。
2つ目は「コトに焦点を当てる」ことです。
いろんなバックグラウンドを持つメンバーが集まって仕事をすると、時に不満や課題が「ヒト」に向いてしまうことがあります。振り返りで課題に向き合う中で、言葉が個人への批判に聞こえてしまうばかりに、事業の課題に向き合うよりも個人同士がうまくやることにエネルギーを割いてしまうという状況も発生しました。
ただ、いまではそういう場面はほとんどありません。私自身、振り返りの中で、何か改善してほしいことをフィードバックする際は「あなたにはこういうことを期待している。だからこの進め方は期待するところとは違う」といった具合に、ヒトではなくコトに焦点を当てたコミュニケーションを意識しています。この心がけも、VUTの皆さんのサポートのもと、組織全体に広げてきたものです。
ちなみに、コトに向かう姿勢はドキュメンテーションを徹底しているからこそ養われると思います。
口頭で話し合うと、向き合っている「ヒト」に焦点が当たりがちですが、課題を文字にすると「コト」が浮かび上がり、それに向き合うことで要因を冷静に分析できます。「あのヒト、あのチームはこれができなかった」という話ではなく、「XXが足りていなかったのか?XXをした方が良かったのか?」と建設的な振り返りができる。VUTにサポートいただいた徹底的なドキュメンテーションのカルチャーは、ここでも威力を発揮してくれていると感じます。
5.全員がオープンマインドでいる
ここまで「組織の壁」を克服する観点で、私たちが肌身に感じたポイントについて述べてきましたが、「組織のOS」をインストールするためには、組織全体が「オープンマインド」でいることが最も大事だと思います。
いくら個人としてクオリティの高い議事録を書くことや権限移譲が徹底されていても、異なる意見や考えを尊重し受け入れられる組織でなければコミュニケーション不全となり十分に機能しません。
オープンマインドな組織づくりのために、私たちはいくつかの工夫をしています。
まず、個人メッセージ(DM)の使用を減らすこと。Slackでは1対1のDMで話せてしまいますが、DMで業務連絡してしまうと、誰がどこで何をやっているのかが他の人からはまるで不透明になってしまいます。コミュニケーションを公にするのがはばかられる雰囲気では、良い議論も進まないでしょう。もちろん個人の機微に触れるような話はやむを得ませんが、そうしたデリケートな話は除き、通常の業務のやり取りはなるべく誰もが見られる場で行うよう全社的に強く推奨しています。
また、社内メンバーが気軽にコミュニケーションできるような場づくりも大事です。たとえば、誰もが宛先なしに些細なことでも気軽に聞けるよう、社内のSlackには「#誰か教えて」というチャンネルが設けられています。こうした取り組みの1つずつは小さな工夫ではありますが、特に社歴が浅いメンバーをスムーズにチームに受け入れ、心理的安全性を保つ場として役立っているのではと感じています。
さらに、以前はさほど多くなかったのですが、メンバー同士の目的のない食事会も意識的に増やすようになりました。コロナ禍以降、私たちもリモートワークやオンラインミーティングがすっかり業務の中心になっていますが、これらに頼り過ぎると、どうしてもその「人」らしさが伝わりづらいコミュニケーションが多くなってしまいます。あえて明確な目的を設けずに食事をともにし、人柄を含めてお互いをよく知る場を意識的に増やすことで、心置きなく頼り・頼られる組織を作ろうとしています。
オープンマインドな組織は、単に情報共有がスムーズになるだけではありません。経営の観点で「任せる力」も高まり、組織全体の力を引き出すと思います。これこそが「組織のOS」をインストールするための肝だと考えています。
私たちの組織づくりは、まだ道半ば
VUTの支援を受けて、全社的にさまざまな変化が起こりました。
しかし、私たちの組織づくりはまだまだ道半ばです。
これからはインストールした「組織のOS」を維持しつつ、さらに高速に大量のトライアンドエラーができる組織を目指したいと考えています。100人なら100人、200人なら200人のメンバーの頭脳を使って問題に取り組み、より迅速に、柔軟に問題解決できる組織となるのが目標です。
現在、私たちJX通信社は国内初となる、官民一体で地域の「情報のライフライン」を作っていくための実証実験や、一般の方が身近なリスク情報をお寄せいただけるNewsDigestアプリの機能刷新など、新たな挑戦を続けています。今後も、報道ベンチャーとしての私たちの歩みにご注目いただければ幸いです。

米重 克洋
株式会社JX通信社
代表取締役
1988年生。大学在学中に報道ベンチャーのJX通信社を創業。全国の報道機関や政府・自治体、企業に対して国内外の災害・事故などのリスクを迅速に検知するソリューション「FASTALERT」や、600万DL超のニュース速報アプリ「NewsDigest」を開発。世論調査の自動化技術やデータサイエンスを生かした選挙予測・分析を手がける。著書に『シン・情報戦略 誰にも「脳」を支配されない 情報爆発時代のサバイブ術』(KADOKAWA)がある。他にAI防災協議会理事などを務める。