スタートアップとの共創で成果を上げる、「戸田建設流」LP出資の活用法
スタートアップと連携して自社の営業力を向上させるなど、オープンイノベーションの成果を上げている戸田建設。事業部側に協業に関心を持ってもらうための工夫や意識していたポイントを聞きました。
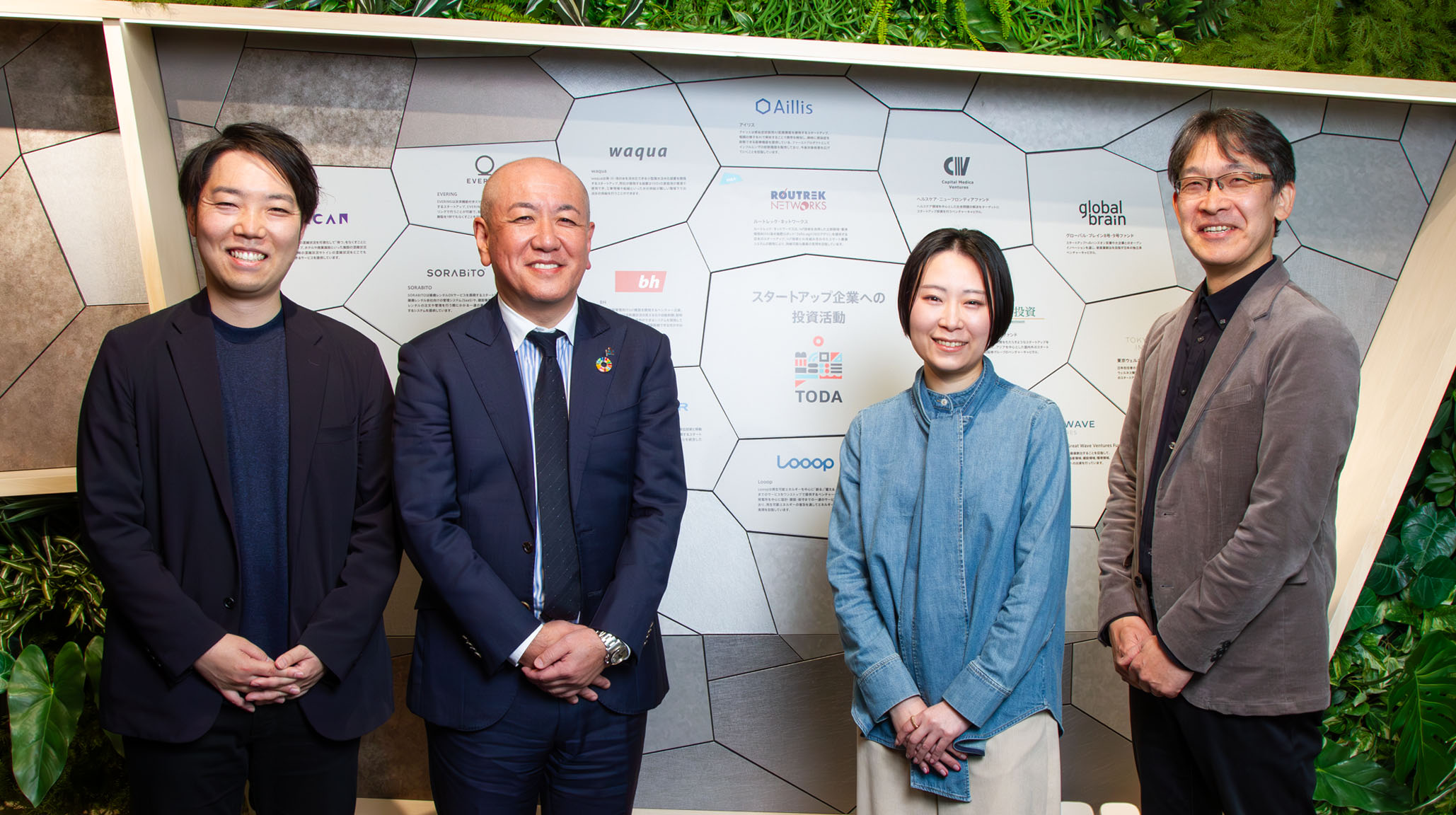
執筆:Universe編集部
大企業とスタートアップの協業は、両者の期待値のすり合わせや社内連携の難しさなどから、多くの企業が課題を感じています。そこで参考になるのが戸田建設の取り組みです。
同社は2021年より独立系ベンチャーキャピタルのグローバル・ブレイン(GB)
なぜ戸田建設はスタートアップと円滑に連携できているのか。イノベーション推進統轄部の工藤 真人統轄部長と同統轄部ビジネスイノベーション部共創投資課の斎藤 寛彰課長に、協業を支援してきたGBの泉 浩之、吉尾 未来にオープンイノベーション推進のために取り組んだことや意識していたポイントについて話を聞きました。
(※所属、役職名などは取材時のものです)
“出資前”からあったGBとの関係性
──戸田建設さんがVCへのLP出資を行うこととなった経緯をお聞かせください。
斎藤:当社はゼネコンとして建築、土木、不動産、再生可能エネルギーなどの事業を展開しています。なかでも建築事業では建物の提案、設計、施工を行っており、お客様の課題を解決する高いレベルの提案をしていくことを常に目指しています。しかし、さまざまなお客様や課題に向き合うにあたって、当社は決して潤沢なリソースを持っているわけではありません。そのためスタートアップという外部の力を借りながら、提案力を補っていくことが合理的だと考えました。
まずはスタートアップの持つ革新的なソリューションをお客様に提案したり自社で活用したりすることを目指し、2018年ごろから本格的な連携を開始しました。その後、より密にスタートアップ協創に取り組むこととなり、GBさんも含めたVCへの出資を行ったという流れです。

──2021年にGBの8号ファンドへ、2024年に9号ファンドへ出資をされました。GBのファンドを出資先に決めた理由も伺わせてください。
斎藤:GBさんには長年の投資実績があり、多方面での成功例を持っています。そういった実績があるからこそ、スタートアップの情報がいち早く集まってくる点が魅力でした。
また泉さんには、8号ファンドへの出資前から、当社のスタートアップ協創を支援していただいています。アメリカのサイズミックというスタートアップが提供しているパワーアシストスーツを、当社の工場で働く技能者に試してもらうために成田市まで来ていただいたこともありました。スタートアップをつなぐだけでなく「現場まで来てくれるんだ」
工藤:9号ファンドへの出資前には、改めてフラットな目線でさまざまなVCさんの比較を行いました。大規模なVC、小規模なVC、特徴的な強みを持つVCなど、さまざまなファンドを検討しました。最終的には私たちのチーム全員で多数決も行ったんですが、8号ファンドでの実績も踏まえてやはりGBさんは外せないと。GBさんとであれば、スタートアップとのよりチャレンジングな取り組みができそうだと判断しました。

「手応えのある協業」にたどり着くまで
──スタートアップとの協業はどのようなプロセスで進められているのでしょうか。
泉:GBがまず行ったのは、戸田建設さんの経営課題と現場の課題を深く理解することです。その後、中期経営計画や注力領域とも照らし合わせながらスタートアップとの協業機会を探索。もちろん戸田建設さんの注力領域や経営方針が変わることもありうるため、ビジネスイノベーション部の皆さんに適宜状況を確認し、最適な協業案を幅広くご提案させていただきました。
また協業推進をスムーズにするため、GBのキャピタリストが講師を務める領域勉強会を実施したこともあります。建設テックはもちろん、宇宙や物流など、戸田建設さんが注目する領域の現状とスタートアップ例をご紹介しました。

斎藤:当初、勉強会は私たちビジネスイノベーション部の社員向けのものでしたが、いまでは全社どの部署からも参加できる会となり、多いときには60人ほどが参加しています。
参加した社員からは「あのスタートアップが面白かった」
泉:質疑応答では素朴な疑問も含めて多様な意見が出ることが多く、協業に関心を持ってもらう良い機会になっていますよね。
斎藤:はい。しかもGBさんにはあらゆる分野に精通したキャピタリストの方が在籍されているので、専門性という意味でも心強いなと感じます。
──実際に進めているスタートアップ協業の中で、特に手応えがあった事例を教えてください。
斎藤:現在進めているThe Chain Museumさんとの取り組みには大きな可能性を感じています。国内外のアーティスト・ギャラリーと連携しているThe Chain Museumさんは、アートに出会う機会と対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「一連の体験をつなぐ」
そんな同社と連携し、建物の発注社様に向けて、アート作品のコーディネートも含めたより価値の高い設計提案をする取り組みを始めました。発注者様の中にはアートに造詣が深い方も多く、The Chain Museumさんの幅広いアーティストネットワークを活かした提案ができていると確信しています。

吉尾:The Chain Museumさんはもともと、作品を個人向けに販売するBtoC事業が中心でした。戸田建設さんと連携していただけたことで、BtoB領域で事業を拡大できる可能性も高まったように感じます。

斎藤:また、建設現場や物流現場などで使えるIoTソリューションを展開するMODEというスタートアップとの連携事例もあります。
実は、最初に事業部側にMODEさんのソリューションを紹介したときには、予算申請の時期を過ぎていたなどの背景から「タイミングが合えば使います」
ここで実感したのはスタートアップ協創におけるタイミングの重要性です。当社では300〜500ほどのプロジェクトが同時進行しており、それぞれの工期や規模によって事業部のニーズが異なります。
だからこそ、事業部側との定期的な情報交換は大切です。いますぐ連携や製品導入につながることはなくても、随時情報共有をしていれば「あのときに聞いたあのスタートアップって…」
また、スタートアップ側も日々サービスを進化させていますから、時が経ってより当社が導入しやすいものになっていることもあるでしょう。タイミングを見計らいつつ、常に全社の最新の課題を見ておくことは大事ですね。

「私たちが協創をストップさせてはいけない」
──スタートアップとの連携を経験したからこそ感じる、協業を進めるためのポイントは何でしょうか。
工藤:事業部との連携とは、突き詰めると社内の人脈活用と言えます。自社の業務をよく理解し、各部門の困りごとや手つかずの課題を把握すること。そして何より、「ちょっとこれ、やってみない?」
斎藤:社内の課題は週1回の定例会議で探索していますが、公式な場以外にも、個人的にさまざまな部門のメンバーとつながりを作り、現場の声を集めています。時には当初の想定とは異なる現場の課題を教えてもらえることもあるので、都度軌道修正をかけて連携の仕方を模索している形です。
また、工藤からは経営レベルの課題も共有されるので、現場と経営、両方の視点から解決策を探っていける体制になっているのもポイントかなと思います。
──GBから見て感じる、戸田建設さんの協業が成功している秘訣は何でしょうか。
泉:実務的なところでいうと、戸田建設さんはまず工事部門でのスタートアップ協業から始められました。工事部門は労働力不足など課題感が大きい部署であったため、サイズミックのようなプロダクトのトライアルも始めやすかった印象があります。社内のアプローチしやすそうな部門から着実に成功事例を積み重ねていけたのがポイントではないでしょうか。
また、イノベーション推進統轄部の方々はスタートアップとの面談にフットワーク軽く、積極的に応じてくださいます。スタートアップへの具体的なフィードバックをすぐにくださるので、取り組みも次のステップに進みやすいですね。

吉尾:戸田建設さんのフットワークの軽さを象徴する出来事もありました。以前、あるスタートアップをご紹介したときに、興味深い展開があって。
斎藤:ありましたね。そのスタートアップの事業内容を聞いてみたところ、事業領域が大きく離れているため、私たちには正直馴染まないと感じていました。
ですが、ダメ元で社内の事業部の方に相談してみたところ「話を聞いてみたい」
工藤:そう、だから私たちが変に判断して協創の可能性をストップさせてはいけないんですよね。
泉:また、全社的にオープンで否定から入らない風土があるのも協業を加速させている理由だと感じます。当社が東急建設さんをご紹介した際も、競合他社でありながら率直な意見交換を交わし、スタートアップへの協調投資にまで発展しました。
斎藤:建設テックに関して言えば、私たち1社がスタートアップの製品を使うよりも業界全体に広まってもらった方が嬉しいわけです。なぜかというと、職人さんはあらゆる建設会社の現場を行き来しているので「XX建設の現場では製品Aを使って、XX建設の現場では使わない」
なので、むしろそこはコンペティターではなく、コクリエーションの考え方で業界内のあらゆる企業さんとも連携していきたいなと。そうすることが真のオープンイノベーションになると思っています。
──なるほど。ちなみにスタートアップとの連携や製品の導入はLP出資を行わずとも可能ですが、LP出資をしたからこそ得られる利点はありますか。
斎藤:私たちが考えるメリットは2つあります。
1つはポートフォリオのバランスをとり、リスクを分散できるという点です。事業会社がスタートアップに出資するためにCVCを設立する方法もありますが、CVCのみではスタートアップの事業領域や成長ステージなどが特定のものに偏ってしまう恐れがあります。LP出資を組み合わせることで、幅広いスタートアップへの投資を行いリスクを分散できるのが大きな利点です。
2つ目は、有望スタートアップとの思いがけない協創が生まれる可能性があるという点です。VCはトレンドに沿った幅広い領域のスタートアップに投資しており、シード期から接点を持っていることも少なくありません。そうした企業と当社のセレンディピティを生み、新たな協業のきっかけが生まれることを期待して、LP出資をしています。
協業の観点でいうと、GBさんの目利き力は魅力です。GBさんが投資するスタートアップであれば、ある程度経営体制やファイナンス面でも認められていて、順調に成長している企業が大半だと思っています。そうしたGBさんのリファレンスがあり、信頼できるスタートアップと連携できるのはありがたいですね。
新たな価値を生むための、両社の挑戦
──最後に、今後のスタートアップ連携でどのような成果を目指されているか展望をお聞かせください。
工藤:スタートアップとの連携による結果を、より具体的に示していきたいです。
たとえば「協創から生まれた付加価値によって案件を受注できた」
また、人手不足が課題の工事部門では、スタートアップのソリューションを使って少ない人員で高い品質を維持していくことは当然目指していきます。もっと言うと、その取り組みが広まって「こういう職場で働きたい」
斎藤:お客様・スタートアップ・当社それぞれがハッピーになる組み合わせをたくさん作っていきたいです。スタートアップの製品を通じてお客様に喜んでいただければ、当社への信頼も高まり、さらにスタートアップにも新たな顧客を紹介できる。三者それぞれに感謝されて、それぞれがWin-Winとなる関係性を数多く生み出していくことがシンプルに目指すべきことかなと思います。

──ありがとうございます。GBとしてはどのような協業支援の展望がありますか。
泉:今後も引き続き、戸田建設さんとスタートアップとの間に入りながら、最適な協業提案や良いつなぎ役としての役割をまっとうしていければと思っています。
また、ビジネスイノベーション部には新たに設計部門を経験された方が参画されると聞いていますので、私たちも設計部門の課題をより深く知ることができるでしょう。これからも戸田建設の皆さんの力を借りながら、より現場に近く、戸田建設さんと同じ目線で協業支援をしていきたいです。
戸田建設さんの取り組みからは私たちが学べることが多くあります。ぜひここでの協業事例をモデルケースにして、他のLP企業さんにも活かしていきたいですね。
吉尾:戸田建設さんとは、これまで私たちもできていなかったことにトライする素地ができてきています。たとえば、戸田建設さんとの連携可能性があるスタートアップを複数社集めて、事業部門の社員の方と交流してもらう独自のイベントなども企画中です。
このような先進的な取り組みに挑戦してくださること自体が本当にありがたいと感じています。こうした挑戦を1つ1つ成功させ、あらゆるLP企業さんの支援にも展開していけたら嬉しいですね。