「優秀なプレイヤーほどマネージャーになってつまずく問題」を、ファインディはどう克服したか
エンジニアプラットフォームを提供するスタートアップ、ファインディ株式会社。同社が独立系VCグローバル・ブレインのハンズオン支援専門チームと取り組んだ、ミドルマネージャーへのコーチング事例についてご紹介します。

執筆:Universe編集部
スタートアップでは若手人材がマネージャーになれる機会がある一方、その経験不足からマネジメントの難しさに直面することは少なくありません。この問題に取り組むため、ファインディ株式会社はグローバル・ブレイン(GB)
そこで今回、コーチングを受けたFindy Freelance事業部長の田頭 一真さん、Findy転職事業部長の末本 充洋さん、Findy Team+事業部 副事業部長の内田 博咲也さん、そして代表取締役の山田 裕一朗さんに、支援を通じて得た気付きや変化を伺いました。コーチとなったVUTのVenture Partner 定国 直樹さんにもお話していただいています。
(※所属、役職名などは取材時のものです)
幹部候補3名に立ちはだかった「壁」
──3人へのコーチングが始まる前、社長の山田さんも定国さんからコーチングを受けていたそうですね。
山田:私に対するコーチングは約3年半前から始まりました。当時新たに採用した方がうまくワークせず、自分自身のマネジメントに課題を感じていたことがきっかけです。以前から弊社の事業支援をしてくれていたこともあり、VUTの一員である定国さんに相談しました。定国さんにしていただいたのは、私の課題の言語化から、メンバーへのフィードバックに対するアドバイスなど多岐にわたります。

──その後、同じコーチング支援を田頭さん、末本さん、内田さんに受けてもらう意思決定をされました。その理由を教えてください。
山田:シンプルに若手育成を重視しているからです。スタートアップで長期的に活躍してもらうには給与やストックオプションだけでなく、成長実感が重要だと思っています。
私は以前レアジョブというベンチャーにいたんですが、マネジメントで非常に苦労しました。メンターのように相談できる人もおらず、壁を乗りこえるまでに長い時間がかかってしまって。
その経験から、ファインディでは少なくとも私がレアジョブにいたときよりも速く成長できる環境を整えたかったんですよね。特に今回の3人には経営幹部になってもらいたい思いもあり、マネージャーとしてステップアップしてもらうためにも定国さんのコーチングを受けてもらうことにしました。
──コーチングが始まる前に、皆さんそれぞれがマネージャーとして抱えていた課題は何だったのでしょうか。
田頭:組織拡大にあわせてマネジメントスタイルを変えられていないのが課題でした。私のチームは短期間でメンバーが15名から40名に増えたんですが、少人数でやっていたころのように事業や人員の状況を把握できなくなってしまって。情報連携ができていないので数字もついてこないし、人もついてこない。非常に辛い状況でした。
また私生活で娘が誕生し、いままでのように自分が長時間労働する“必殺技”が使えなくなったのも状況を難しくしていたと思います。
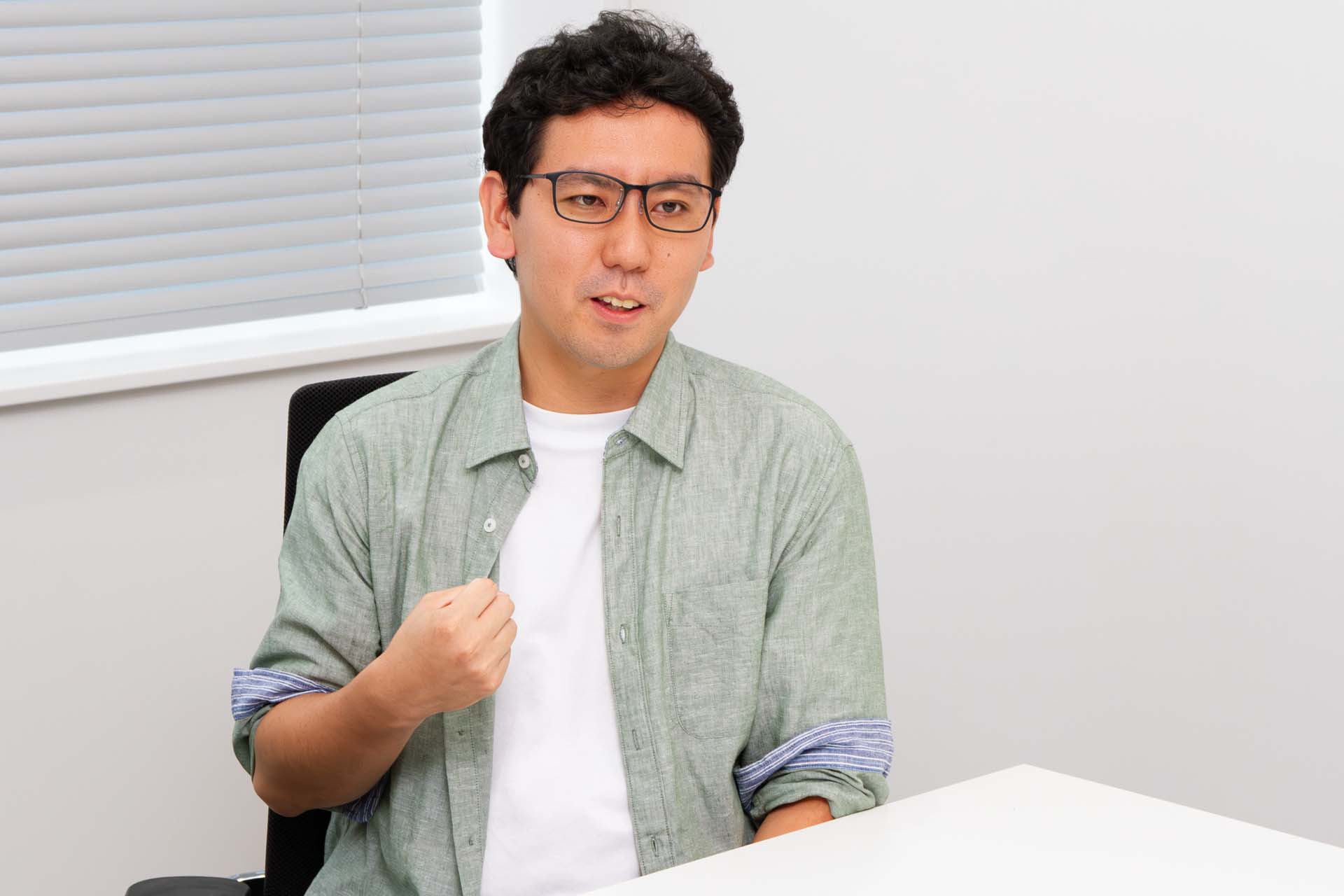
末本:私の場合は、管轄する組織が事業の伸びに合わせて、セールス、マーケティング、プロダクトなどさまざまな機能を持ったこともあり、単なるマネージャーからゼネラルマネージャーへの移行が課題でした。20人程度の組織なら気合いと根性でまとめあげられましたが、それ以上は未知の領域で。
直接話したことのないメンバーも出てくるので、指示出しも難しくなります。いかに全メンバーに納得してもらえるコミュニケーションができるか、そのためにいかに自分の器を大きくできるかがテーマでした。
内田:私も末本さんの壁と似ています。2人だった組織が18人に拡大し、「誰に何を任せるか」
加えて私は、自分がプレイヤーだったころのスピード感でチームを動かそうとする問題も抱えてましたね。当然私1人がプレイングするときのように組織は動かないので、そのギャップにも苦心しました。
定国:皆さんに共通しているのはプレイヤーとして本当に優秀だということです。だからこそ山田さんからマネジメントを任せられたわけですが、プレイヤーとマネージャーでは視点を変えなければいけません。その観点で皆さんと個別に対話しながら、それぞれの課題をどう克服するかについて意見交換を重ねました。
それぞれのコーチングで語られたこと
──定国さんとのコーチングの中で印象的だったやりとりや気付きがあれば教えてください。
内田:もっとも変わったのは「見据える時間軸」
気付きを得たきっかけは「重要度と緊急度のマトリックス」

末本:私は定国さんとは、マネジメントの話だけでなく、自分の弱さも率直に話させてもらいました。印象に残っているのは「最近モヤモヤしていて、心が折れそうです」
結果、「事業の伸び悩み」
定国:そのやりとり、覚えてます。私も過去にとことんパフォームできなかった時期がありました。その経験も踏まえて「私がキツかったのはこういう条件が重なったときですが、末本さんはどうですか?」
──マネジメント論の話だけでなく、自己分析のようなこともされていたんですね。田頭さんはどうですか?
田頭:私はメンバーに悩みを吐露する重要性に気付きました。事業部長になったばかりの頃は、人を惹きつけるリーダーは完璧な振る舞いをすべきだと思っていたんですが、そうすればするほど人が離れていってしまう感覚があって。
定国さんからは「リーダーシップとは単にビジョンを示して牽引するだけではない」
定国:どんなリーダーシップを発揮すべきかはそれぞれの個性もあると思います。強い言葉で発破をかけるスタイルももちろんありますが、それは田頭さんらしくないよねと話し合いました。

──定国さんはコーチング時にどのようなことを意識しているのでしょうか。
定国:私から「こうすべきだ」
また私はスタートアップで働いている方にはリスペクトの念しかありません。「皆さんすごいな」
山田:定国さんは常にポジティブに話されるんですよね。私たちがネガティブなことを話してもポジティブに返してくれる。だから皆話しやすかったんじゃないかな。
山田社長も驚いた、3名の急成長
──それぞれコーチングを経て、自分の意識や仕事の進め方が変わったと思った瞬間はありましたか?
内田:先ほどの話ともつながりますが、時間の使い方が大きく変わりました。1年先を考えて行動すると、逆に3ヶ月先のことには時間を使えなくなるので、短期のアクションをメンバーに任せられるようになってきました。
定国さんとは実務についても話し合いましたね。重要度と緊急度のマトリックスを見ながら、「ここは任せたほうがいい、ここは内田さんがやったほうがいい」
末本:まだ取り組み中ではありますが、メンバーの視点から自分や事業がどう映っているかを意識するようになりました。視点が私1人から複数になったとも言えると思います。
今日入社した人と半年前に入社した人では、同じ言葉でも捉え方が異なることがあります。プレイヤーのときは自分1人の視点で良かったのが、マネージャーではそうはいきません。言葉の使い方や単語の選び方、見られ方を意識することで、リーダーとしてチームを特定の方向に導けるようにもなってきました。
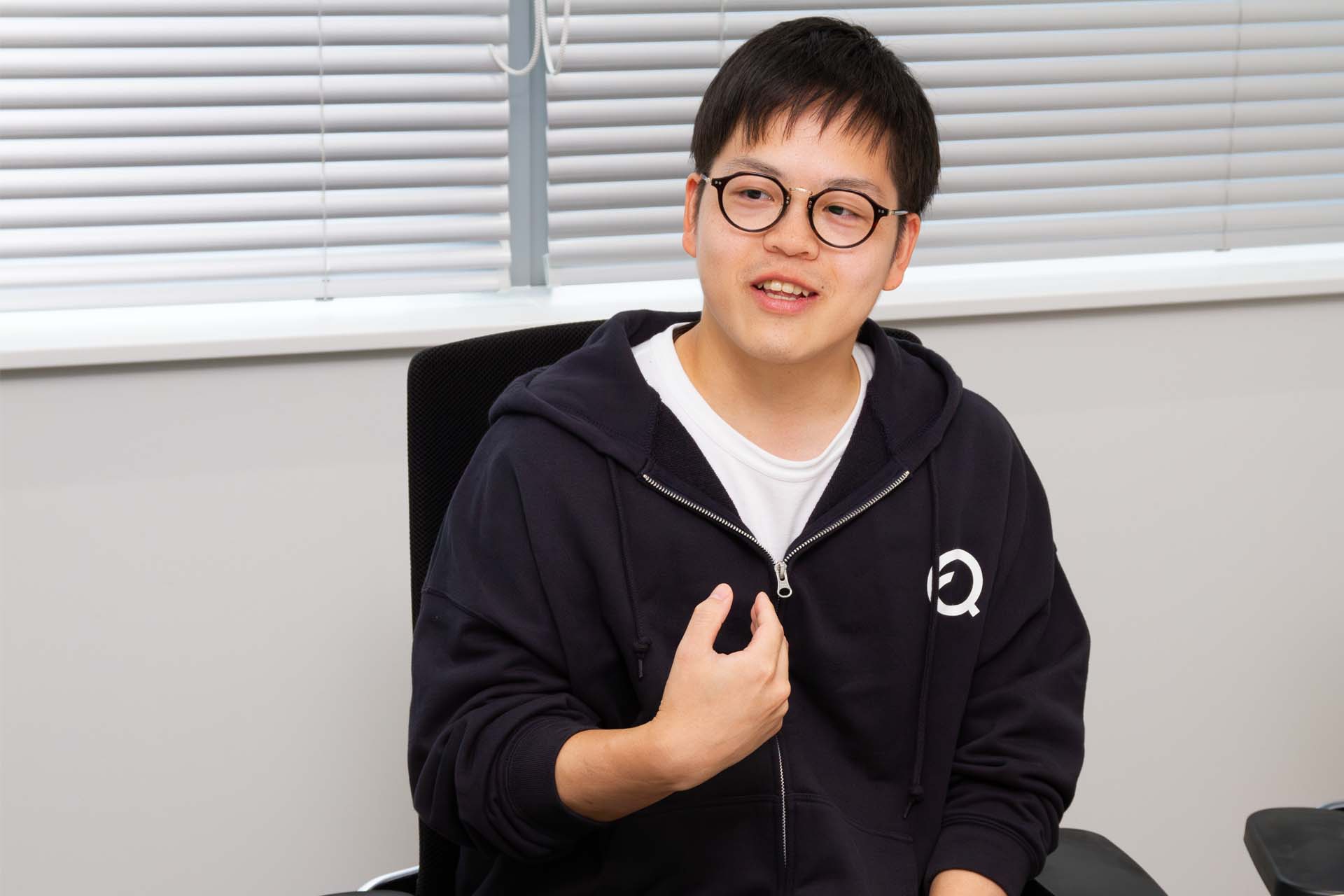
田頭:私は事業責任者としての覚悟ができました。事業がうまくいっていなかったときは「なんでファインディはこの事業をやっているんだっけ?」
「自分はいまこの会社で重要な意思決定や推進をできる立場にいるのに、何を悩んでるんだろう」
──山田さんの観点からも、皆さんの変化を感じた場面があれば教えてください。
山田:全員すごく良い成長をしていると感じます。内田は自分がプレイヤーだったころの基準でメンバーと接してしまうことがあったんですが、随分丸くなりました。いまでは社内を横串でまとめる仕事や難しい交渉ごとなど、相手の気持ちを踏まえなければできない仕事もこなしてくれています。
末本には事業PLの最も重たい部分を任せていたんですが、よく耐えてくれました。次につながるいい経験になったはずです。あと最近、末本のチームのメンバーと話してると「末本さんとの対話でこんなことに気付きました」
田頭はタフになりましたね。しかも彼は事業への愛も強いので、二の矢、三の矢を必ず考えてくれます。事業も順調に伸びてきているので、田頭のチームは私がいま1番心配しなくていい組織になっていると感じます。
私が経営をやってて1番嬉しいのは、こういう皆の成長を間近で見られることです。ビジョンの達成と同じくらい、本当に嬉しいなと感じます。
ファインディの10年、20年先を見据えて
──マネージャーとしての変化を感じたいま、今後組織や事業にどう向き合っていきたいと感じていますか?
内田:組織が大きくなる中で重要だと感じたのは「メンバーや事業に期待をし続けられるか」
人は周囲から「期待されていない」
末本:私は組織というレバーを引きながら事業を大きくしていきたいです。
メンバーがご機嫌な状態で仕事ができることが戦略のカードの1つになると思ってます。内田の話ともつながりますが、人はモチベーションによってパフォーマンスが大きく変わります。人の心の機微を読みながら“感情マネジメント”することも、事業戦略と同じくらい重要ですね。
田頭:事業の踊り場を作らず、成長させ続けることを意識したいです。
最近うちの事業部ではマーケティング予算をつけて新たなチャレンジをさせてもらえているのですが、それも事業が一定伸びてきているからだと思っています。逆に、事業が停滞するとそういったチャレンジも抑えられてしまう。
社外のユーザーへの価値提供をすることが社内の機会も増やします。社外と社内の価値提供が接続しているという気付きを得られたいま、事業責任者として成長させ続けることに心血を注いでいきたいですね。

──最後に、今回のコーチングを通じて、スタートアップが人材育成を行う価値として感じたことを山田さんの観点から教えてください。
山田:スタートアップって急成長すると楽しくもあるんですけど、しんどいことも多いんですよね。その中で今回のような人材育成の取り組みはすごく必要だと感じます。
スタートアップは若くてもマネージャーになれるのがいいところです。大手企業だと40歳くらいでやっとマネージャーという感じですが、スタートアップだと20代からそういう機会があります。ただ、若いからこそ誰もが始めはつまずいてしまう。「マネジメントとは人の強みを生かすこと」
今回のように経験豊富な人が困難の乗り越え方をコーチングする支援が当たり前になっていけば、もっと速く伸びるスタートアップが増えるんじゃないかなと思います。
スタートアップでは熟練の経験者をどんどん採用していくのも大事ですが、同じくらい初期メンバーや若手が残って上に上がっていくのも大切です。短期的な成長だけを考えるなら、経験者を採用する方が正解に見えるかもしれない。でも、10年、20年先を見据えて、新しい事業を作り続けることを考えたら、経験者も若手も両方必要なんですよね。
長期で勝ち続けるスタートアップや、もっと大きなスタートアップを作るためにも、若手人材への支援はすごく大事だと思います。GBさんにはぜひこういう支援を続けてもらえるとありがたいですね。