注目のスタートアップが集結!GBAF 2021「Startup Pitch Battle 2021」レポート(2)
グローバル・ブレインが2020年末からの約1年間に投資を決定したスタートアップ企業のうち、今注目の領域10社を選定しました。

執筆: Universe編集部
12月10日に開催したグローバル・ブレイン(以下、GB)の年次カンファレンス「Global Brain Alliance Forum 2021(GBAF 2021)」の終盤では、GBが2020年末からの約1年間に投資を決定したスタートアップ企業のうち、今注目の領域の10社による「Startup Pitch Battle 2021」を行ないました。
今回は後半にプレゼンを実施した、下記5社のご紹介です。
エディットフォース 小野 高氏

最近ではゲノム編集関連技術がノーベル化学賞を受賞したことや、新型コロナウイルスに対するワクチンとしてRNAが脚光を浴びています。同社はPPR技術を新しい素材(モダリティ)として、DNA/RNAを標的とした創薬における研究開発を展開する、九州大学発のバイオベンチャー企業です。独自の技術を強みとして、今までにない治療薬を創出することをミッションとしています。
ゲノムとは、簡単に言うとある生物を構成する全ての遺伝子情報のこと。遺伝子はDNAに記憶されており、A、T、G、Cの4種類で構成されています。ヒトでは、約30億塩基対のDNAの中に約2.2万個のタンパク質遺伝子が含まれており、それらが組み合わさって体ができています。今まで主に偶然に頼って変異させていた遺伝子組み換えと違い、同社のゲノム編集技術では狙った場所にのみ変異を起こすことが可能です。
バイオ産業は、2030年には全GDPの2.7%(約200兆円)の市場に成長する見込みです。農業、化学工業、メディカル領域において、ゲノム編集の幅広い応用例が出てきており、同社は医療・医薬の領域で活動しています。
ドラッグストアや外来で手に入る薬は、主にタンパク質を標的にしていますが、タンパク質を標的としても治らない病気は多く、最近はRNA/DNAを標的とした医薬品が注目されています。DNA/RNA編集を含む遺伝子治療領域の市場はますます拡大すると予測され、さらにアンメット・メディカル・ニーズ(※)の大きい遺伝子疾患に対する治療薬が主役になるとも言われており、遺伝子関連領域の医薬品市場は大きく成長が見込まれます。 (※)アンメット・メディカル・ニーズ :いまだに治療法が見つかっていない疾患に対する医療ニーズ。具体的には癌、認知症などの重篤な疾患のほか、不眠症や偏頭痛など生命に支障はないがQOL改善のために必要とされるもの
RNA標的は生命の本質に近いため、より効率的に、より大きな治療インパクトを与える可能性があり、これまでのタンパク質標的医薬品の全てを置き換え、60兆円という市場規模に成長するポテンシャルを持ち合わせています。
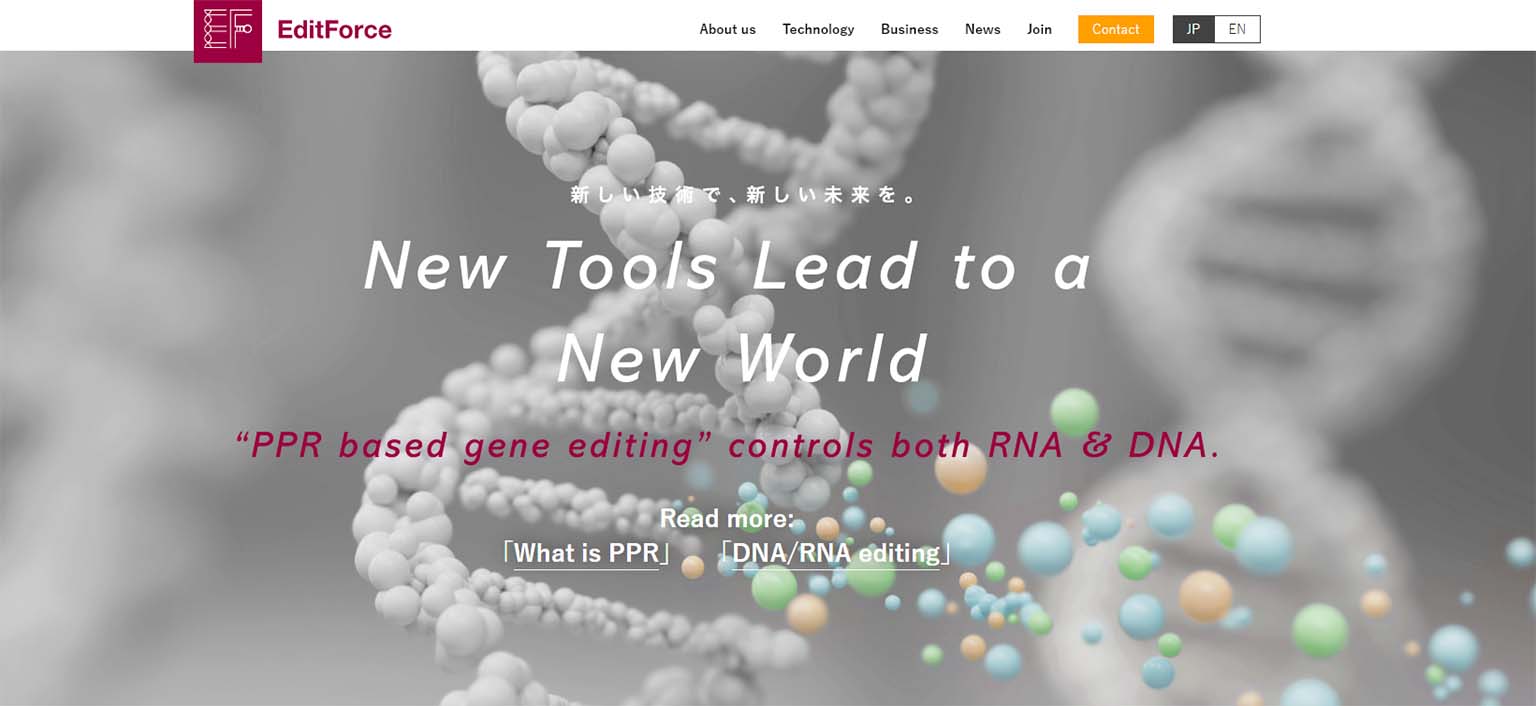
ゲノム編集領域の競合他社は海外に多くありますが、同社はタンパク質をベースとするRNA編集ツールとしてはオンリーワンの存在です。既存ツールではできない操作が可能な画期的技術であり、基盤技術は特許が成立しています。
ビジネスモデルとしては、製薬会社・アカデミアなどとタイアップするハイブリッド型(プラットフォーム×アーリーライセンスアウト)となっています。創薬ベンチャーや大学と共同研究をすることで新しい薬のタネを作り、製薬会社からPPR技術のライセンス料やロイヤリティを支払ってもらうモデルです。またどのタイミングで共同研究を始めるかについては、製薬会社と同社で慎重に協議し、リスクの低減や果実の最大化を図っています。現在は7つのパイプラインを開発中で、小野氏は「今後は医薬品にとどまらず、ケミカル、アグリカルチャーに向けて広げていきたい」と話しました。
TOUCH TO GO 阿久津 智紀氏

「TTG-SENSE」という無人決済店舗システムを開発し実用化している同社は、高輪ゲートウェイ駅に同システムを導入した実店舗を運営しています。入口ゲートで人の入店を検知すると、天井と棚などのカメラやセンサーを使って、来店客が手に取った商品を全てリアルタイムでトラッキングします。そのため来店客はレジで手に取った商品をスキャンをする必要はなく、そのまま決済することで買い物を完了させることが可能となります。得られたデータはマーケティングにも活用できます。
同社は本事業を通じて人手不足を解決するとともに、大企業発の新規事業創造に貢献したいと考えます。2030年、労働需要7,073万人に対して、人手は644万人も不足すると言われています。それに伴い、サービス・小売・医療などの人手不足領域では、さらなる賃金上昇が見込まれます。世の中のリソース・アセットは大企業が保有していますが、大企業内における新規事業は、予算・稟議・外部環境などによるスピード不足や、売上規模・撤退基準・既存事業とのカニバリゼーションといった文化的ギャップ、規則前提・人事的制度などの組織制度構造など、多くのハードルが存在しています。
JR東日本スタートアッププログラムは、駅や鉄道などの経営資源、グループ事業における情報資源を活用したビジネスやサービスの提案を募り、アイデアのブラッシュアップを経て、新たな価値の創出を目指すプログラムです。同社はこのプログラム内で技術力を持つスタートアップと出会い、ジョイントベンチャーとして立ち上がりました。
スタートアップが持っている技術力と大企業が持つアセットを組み合わせて、早期に社会実装することを目的に設立され、チームは大企業からの出向者とスタートアップのプロパーメンバーで構成されています。
このような背景で設立した企業であるため、大企業とのアライアンスを組むことを得意としています。また開発力も強みで、最先端のIT技術、デバイス開発力、オペレーションノウハウを活かし、同領域におけるシステム提供を実用化しました。
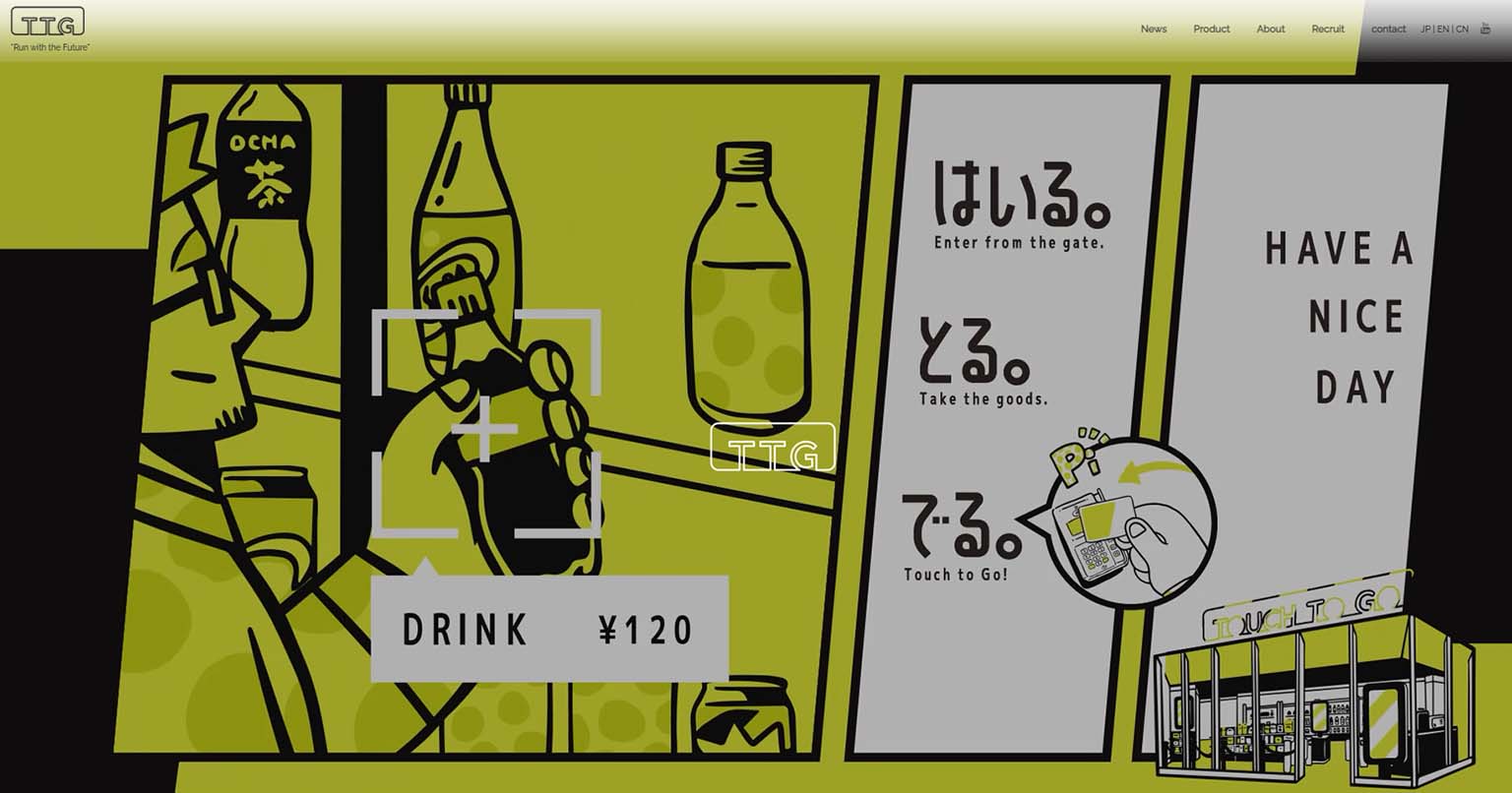
コロナ禍の影響により、非対面&マイクロマーケットビジネスの需要がさらに拡大していることを受け、高速道路のSA、大学やオフィスビル、マンションなどの売上規模の小さな売店、感染リスクの高い病院の売店などで導入が進んでいます。また、ファミリマートとは資本業務提携し、1,000店舗導入に向けて準備中とのことです。
阿久津氏は「M3やモノタロウもカーブアウトして大企業から切り出した事業です。日本特有の大企業のアセット・リソースを活用することで、大企業からスタートアップを生み出し、世界で闘える事業を作る、日本独自の起業のロールモデルを作りたい。これから迎える省人化に対して、便利な世界をつくっていきたい」と話しました。
UPSIDER 宮城 徹氏

創業直後のスタートアップから、上場準備中の企業や上場企業も利用可能な法人カードを提供するUPSIDER。同社の年間成長率は1,500%、利用継続率99%と急成長を遂げています。
同社は、従来のカードより非常に大きな利用限度額を提供することで、未上場企業の成長投資の資金繰りを支えます。また自動仕訳がしやすいように、カードごとに保有者、部門、目的などをタグ付け。会計処理を簡便にしています。加えて各取引にメモや領収書を付加することで、会計処理に必要な情報を1 stopで集めることができます。
安心面では、Web上でカード毎のロックや予算などのコントロールが可能。退職者管理もできるため、不要な支払いや不正な利用が発生しづらい仕様になっています。

同社は自社サービスを経費を支払う法人カードサービスではなく、財務の課題を解決するSaaSと位置づけます。ビジネスを止める存在ではなく、伴走し加速化できる存在でありたい、社会に変化を創る金融サービスとして経済を前に動かしたいという思いで、審査のスピードや問合せの即レス対応など、時間の観点でもお客の無駄を省くことを大切にしているといいます。
法人カードは多くの企業が利用しており、“どれを使うのか”が論点です。また近年ではWebサービスが多く台頭していることから、クレジットカードの利用機会も増えています。ガラケーからスマートフォンへと進化したように、同社は次の世代の法人カードを通して、ビジネスを加速化する総合金融サービスを目指しています。
Shizai 鈴木 暢之氏

薬局などでよく見る化粧箱を発注しようとした場合、国内の業者に見積もりを取ると安い企業と高い企業では2倍ほどの価格差が発生します。このようなコスト差が発生する理由には、大きく2つの点が挙げられます。
1つは、価格構成要素の“非”最適状態。包装資材のコスト構成要素としては、「素材コスト(原紙 / 元素材)」「工賃(人件費)」「配送費」「特殊な加工」の大きく4つに分けられます。要求仕様に対して、4項目の組み合わせによりコストが決定しているため、価格にばらつきが起こるというわけです。理由の2つ目は様々なレイヤーで複数プレイヤーが介在していることによる「多重引受構造」にあります。
同社は「最適な工場選定+コスト最適化+見積速度向上」を実現するソリューションを提供。サービスを使用することで、同じ品質のものが最大20〜30%安く購入できます。全国に500以上の優良な一次製造元ネットワークを構築し、注文の要件と配送エリアに応じた最適な工場を組み合わせることで実現可能にしました。
実際にサービスを利用するある事業者では、段ボールや、コスメ用化粧箱の作成を置き換えたことで約40%のコストダウンを実現。同社自身も2020年4月の本ローンチ以降、Q単位で130〜150%成長を遂げています。

国内のパッケージ印刷市場は1.4兆円、国内容器・包装材市場は4.5兆円規模ある中で、テクノロジー充当率が低いレガシー巨大産業です。国内需要サイド、EC化率向上に伴って加速するエンタープライズ企業のEC参入や、D2Cスタートアップの増加と成長、マイクロユーザーのshop立ち上げなどを要因に、2025年の国内EC市場は27兆8,000億円に上ります。
グローバルの状況をみても、ここ数年で同業他社であるUSのLumiが昨年末Narvarに買収されたり、EUのpackhelp、インドのBIZONGO、中国の小像智合などが大きな調達を行なったりと、EC比率の向上に応じた海外プレイヤーが台頭しています。社会的な背景としては、SDGsの一環として脱プラ / 非アルミなど、環境対応アクションが一般化したことも追い風になっています。
鈴木氏は「巨大産業のテクノロジー充当による経済合理性を作りつつも、SDGsや脱炭素など30年後に向けた社会合理性の交差点にしっかりと事業を作っていきたい」と話しました。
カウシェ 門奈 剣平氏

中国で圧倒的なユーザー数を誇るECのアリババを、たった6年で追い越した拼多多(ピンドゥオドゥオ)はナスダックで時価総額10兆円以上を付けています。彼らが成長した秘密は1人だと買えないECであること。日本の小売を盛り上げるにはこれしかないと立ち上げたサービスが「カウシェ」です。
カウシェで商品を購入するには自分以外にも1人以上が購入することが必要で、商品を購入したいユーザーが、他のユーザーを連れてくる仕組みになっています。既存ECよりも購買フローにおける拡散力が高いことから、事業主は広告費を削減し、その分他ECと比較して10〜30%低い価格設定を実現することができます。現在は購入頻度が高く、単価が低い食品や日用品を主に扱っていますが、今後は市場規模の大きい家電(2022年1月リリース済)や衣料品なども販売予定といいます。
現在は子どものいる家庭を中心に日本全国で急速に普及。リリースから1年で累計30万ダウンロード数を突破し、GMVはリリースから33倍の成長を遂げています。

日本のEC化比率は8%であり、90%近くが未だにオフラインで販売されている状況です。コロナ禍の影響を大きく受けている日本に対し、中国ではオフラインに代わるオンラインのショッピング体験が次々に立ち上がっていることもあり、「日本のECはもっと進化すべきであり、その可能性を秘めている」と門奈氏は話します。
カウシェ最大の強みはCAC(新規購入者の獲得コスト)で、大手ECと比べると大幅に低い実績を実現しています。シェア買いという新しいショッピング体験を通じて、最終的には日本のEC化比率向上に貢献し、あらゆるモノ余りの課題を解決するべく、今後5年でGMV1兆円/年の達成を目指しています。
以上10社、どのピッチも熱のこもった内容ばかりで、発表を聞く審査員の皆様の真剣な眼差しも印象的でした。
なお、GBAF 2021「Startup Pitch Battle 2021」受賞企業として、オーディエンスの投票によって決まるAUDIENCE AWARDに株式会社TOUCH TO GOが、プレゼンが最も上手かった企業に送られるGBAF AWARDに株式会社スマートバンク、そして審査員が選ぶPITCH PANEL AWARDに株式会社UPSIDERが選ばれています。
