注目のスタートアップが集結!GBAF 2021「Startup Pitch Battle 2021」レポート(1)
グローバル・ブレインが2020年末からの約1年間に投資を決定したスタートアップ企業のうち、今注目の領域10社を選定しました。

執筆: Universe編集部
12月10日に開催したグローバル・ブレイン(以下、GB)の年次カンファレンス「Global Brain Alliance Forum 2021(GBAF 2021)」の終盤では、GBが2020年末からの約1年間に投資を決定したスタートアップ企業のうち、今注目の領域の10社による「Startup Pitch Battle 2021」を行ないました。
本年審査員賞の審査を行なったのは、次の皆さまです。
- 起業家・エンジェル投資家 有安 伸宏 様
- ヘイ株式会社 代表取締役社長 佐藤 裕介 様
- 株式会社ACSL 社外取締役 杉山 全功 様
今回、その模様を2回に分けてお届けします。
RECEPTIONIST 橋本 真里子氏

従来、内線電話が主流であった受付は、来客者、来客対応者、社員それぞれの生産性を下げていると言われています。また、コロナ禍の影響で多様な働き方が生まれたことにより、特定の社員に出社・来客対応が集中してストレスを抱えてしまうケースも発生しており、受付の在り方は変化を求められています。
RECEPTIONISTは受付システムを中心に日程調整、会議室の予約・管理を通じて、ビジネスのコミュニケーションをワンストップで効率化するサービスを提供しています。

受付システムは、内線電話の代わりにiPadを使用。QRコードを活用すれば完全非接触で受付することが可能です。着信音やビジネスチャットを使って、担当者を直接呼び出すことができ、来客データは全て自動で保管されます。セキュリティゲートと連携したり有人受付と併用して使うシーンも増え、解約率は0.6パーセント。今ではスタートアップから大企業まで幅広く導入しているとのことです。
日程調整ツール「調整アポ」も展開しており、ホスト側は予約用のURLを発行し送るだけ。ゲスト側がそのURLから日時を選ぶと、日程調整が完了します。GoogleやOutlookといったカレンダーツールと連携し、空き時間の自動抽出や複数人での日程調整、Zoomなど会議用URLの自動発行から会議室の予約まで、一気通貫で調整できます。Salesforceとも連携し、日程調整と共に顧客情報も自動で生成できるため、マーケティングやセールスにも活用されています。同サービスも幅広い企業に導入されており、病院といった企業以外の使用事例も生まれているようです。
Antway 前島 恵氏

近年、共働き世帯は急激に増加し、今では全国で1,200万世帯にのぼると言われています。共働き世帯は常に忙しく、家事・育児・自分の仕事と分刻みのスケジュールをこなしています。
共働き子育て世帯向けのお惣菜デリバリーサービス「つくりおき.jp」は、大人2人、子ども2人想定の量を3食もしくは5食の2プランから選択が可能。食事内容におけるメニュー選択機能はなくし、サブスクで週に1度、冷蔵でまとめて自宅に届きます。選択肢を敢えて制限することで、子育て世代の手間を削減しています。
注文はLINEで「つくりおき.jp」のアカウントを友だち登録し、注文・配送日を決定、その後クレジットカード or LINE Payで決済をするだけで完了。簡単に始めることができます。
同社はただの食事宅配サービスではなく、安心して家庭内の炊事にまつわる家事の全てを任せることができるサービスです。このサービスにより、時間やマインドシェアを開放し、「バリバリ仕事がしたい」「自分の時間を大切にしたい」「家族との時間を豊かにしたい」という共働き世帯の想いを解決。家庭内の無償労働をサービス化していくことによって、新たな市場を切り開いていきたいと考えています。

同社の成長率を牽引する強みは、敢えて自社で製造設備を持つことで、最速翌日にはサービスに反映ができるプロセスを確立したところにあります。ユーザーからLINE上でメニュー別にフィードバックを受け取ると、その嗜好DBを蓄積し、レシピやオペレーションに反映。数百坪の規模を持つ自社キッチンで即座に改善を施し、高速な改善・FBサイクルを回しています。
これにより大量調理に最適化された数千件のオリジナルレシピと、10万件以上の嗜好データを組み合わせたメニュー構成の実現を可能にしました。
今後は日用品や洗濯物、家電といった生活に必要となるあらゆるものをサービス化し、各家庭が必要とする物、感じている課題を解決できる存在になることを目指しています。
リセ 藤田美樹氏

代表の藤田氏は弁護士として企業間の紛争を専門に18年間勤務していました。特に中堅・中小企業で「契約書がもう少し良い文言になっていれば、紛争を防げた」という事例が沢山発生していることを知り同社を起業します。
実際全ての契約書を弁護士に見てもらうには、費用がある程度かかります。そこで最先端のAIテクノロジーを用いて、全ての企業に合理的な価格で専門分野の知見を提供し、世の中の紛争を少なくするために貢献するサービス「LeCHECK(以下、リチェック)」を開発しました。

リチェックは、少人数の法務を支援するクラウド型リーガルテックサービス。AIによる契約書の自動レビュー、英文契約書の機械翻訳、自社ノウハウの蓄積など様々な機能を合理的な価格で提供し、契約業務の効率化とコスト削減をサポートします。
相手から届いた契約書をアップロードすると、それぞれの立場に応じて不利益なところや抜けているところを見つけ出し、欠落条項を指摘。世の中には様々な類型の契約書があるものの、もめるポイントは大体決まっているため、もめやすいポイントに関して事前に備えることが可能です。また、自社ひな形の登録・条文検索も可能で、自社ノウハウの蓄積、自社法務のDXにも活用できます。加えて過去の契約書や自社ひな形と比較する、文書比較機能や、締結済みの契約書を管理するキャビネット機能などを備えています。
紛争は時間とお金がかかるだけでなく、人の心に非常に大きな負の感情を残します。藤田氏は、「ひとたび紛争が起こってしまうと、その後大半が取引を続けることが難しくなってしまうため、費用をかけずにできる限り事前に防いでいくことで、スムーズな取引と幸せに働ける世界を目指しています」と語りました。
DAIZ 井出 剛氏
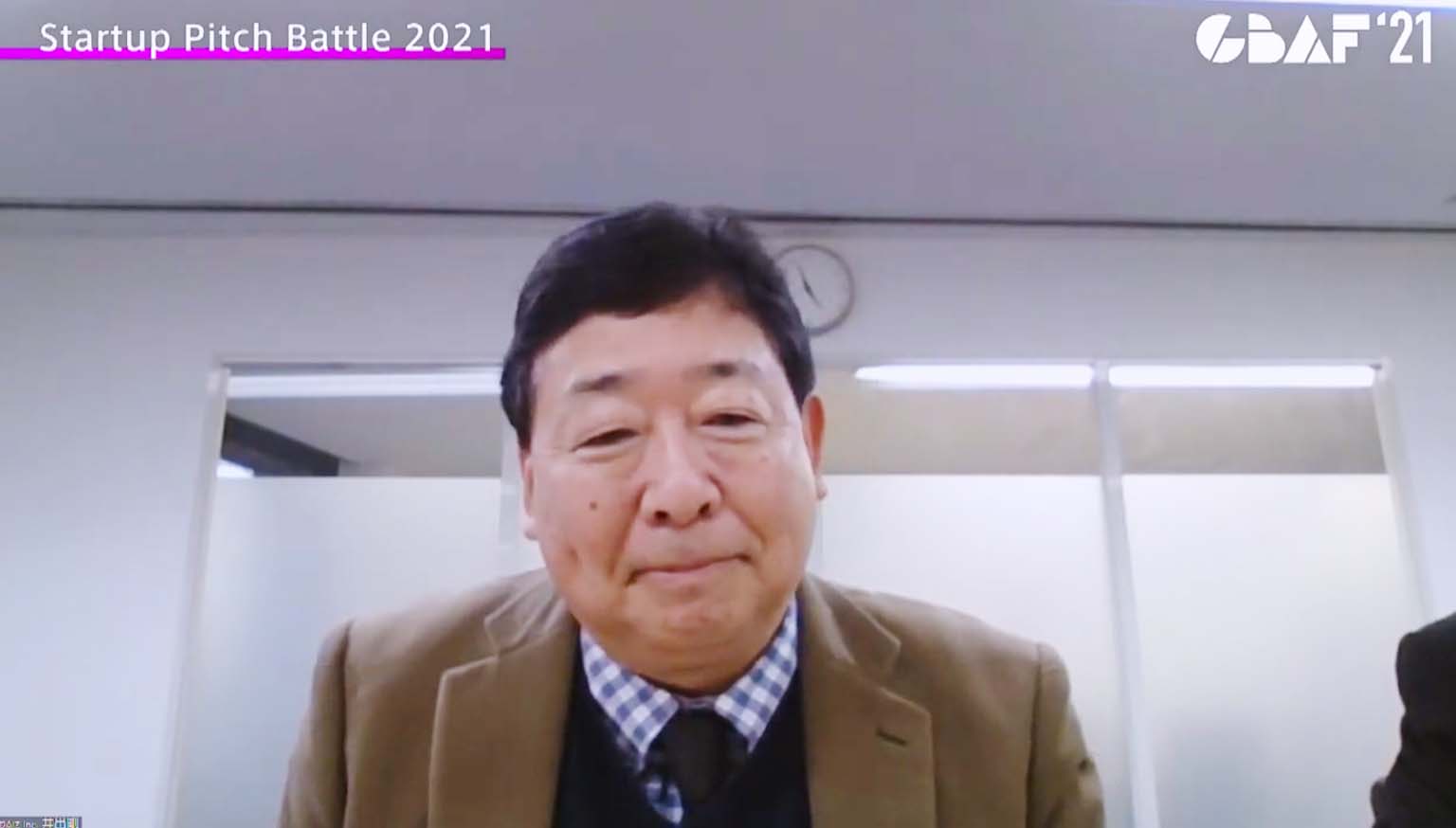
日本でも植物肉を使った商品を目にする機会が増えつつありますが、米国ボストン、ニューヨーク、シアトルなどでは、魚・豚・鳥・牛に加えて、必ず植物肉が販売されています。世界中で懸念されている温暖化のことを考えると、地球上で農業できる場所は限られてくるかもれません。温暖化が進むことで最初に影響を受けるものの1つに農業(=食)があります。
植物肉市場が拡大する背景として、まず第一に人口100億人に達する2050年に起こると言われているタンパク質危機が挙げられます。また、豚コレラの蔓延により豚肉価格が2019年比で2倍になっていることや、フレキシタリアンの登場により、美味しい植物肉のニーズが生まれていること、SDGsによって、環境に優しいプラントベースのプロテインが普及していること、ビヨンドミートの上場によって、植物肉の認知が高まったことも要因です。

同社は世界中で植物肉に取り組んでいるあらゆる企業へ原材料を供給することを目指し、植物肉における原材料を作っています。一般的に大豆から作られる植物肉は、ほとんどの原材料がでんぷんや油をしぼったあとのカスに、いろんな添加剤を加えているものが主流です。しかし同社は大豆を発芽させるプロセスに独自の技術を持っており、その過程で鳥や豚肉・牛肉のような味に近づけていきます。井出氏は原材料がよければ、植物肉は普及していくはずと話します。
現在はイオンやフレッシュネスバーガー、コストコ、ニチレイなどと共同で商品開発を行なっています。植物肉の普及に関しては日本は遅れているものの、世界中には植物肉に関わる会社が膨大に存在していて、それら全ての企業が顧客となりえます。原材料にこだわって製造・供給する企業は世界的にもまだ少ないことが、同社の強みです。
スマートバンク 堀井 翔太氏

キャッシュレス決済は世界各国でその比率が上昇し、現金の流通量が減少するのは不可逆な流れとなっていますが、コロナ禍における非接触経済の中でさらに拡大しています。そのような潮流にある中、日本における毎月の支出はいまだに現金で管理されていることが多い状況です。
同社が提供する家計簿プリカB / 43は、家計簿のアプリとVISAのブランドプリペイドカードがセットになったサービスです。アプリに生活費をチャージして、付属のカードで決済をすると、使った加盟店と金額をリアルタイムに表示。「今いくら使える」がひと目で分かるため、使いすぎを防止することができます。
またアプリ上でお金を貯めておいたり、分けて管理することも可能。例えば旅行に向けてお金を貯めておきたい場合、特定のポケット(フォルダ)に残高を移動させることで、決済時に差し引かれることなく貯金ができます。アプリにチャージしたお金は、スマホがあればセブン銀行ATMでいつでも出金することが可能です。現在リリースしているiOSの数字だけで、月間のGMVはリリースから1年以内で数億円を突破するなど、順調な成長を続けています。

また、個人の家計管理だけでなく夫婦や同棲しているパートナーとの家計管理における問題も解決する、B / 43 ペア口座も注目です。
共同の銀行口座を開設して管理する方法では、名義人でないと残高を確認できない問題がありました。また同棲カップルの場合、クレジットカードなどの家族カードは作れないため、パートナー側に立て替えた金額を共有し、請求・精算をしなければなりません。
同サービスではパートナーと共同で口座を開設でき、その口座に対してお互い入金・出金も可能です。B / 43の提供するカードを使って決済をすれば、どちらが決済してもタイムラインに履歴が反映されるようになっています。
さらにアプリ上で簡単に口座の切替や、個人の口座とパートナーの口座の振替も可能。個人口座を開設済みのパートナー同士であれば、お互いがQRコードを読み合わせるだけで、すぐにペア口座が開設できます。ペア口座ユーザーの継続率、利用金額、頻度は個人口座より高い状況といいます。
これからは家計簿機能に加え、生活費管理の問題や、資産管理、資産運用といった課題も解決していく予定とのことです。
後編では、下記5社をご紹介します。
- エディットフォース株式会社
- 株式会社TOUCH TO GO
- 株式会社UPSIDER
- 株式会社shizai
- 株式会社カウシェ