パーソナライズAIの時代へ──Supermemoryが挑む生成AIの「記憶の課題」【GB Tech Trend #148】
ファイル・文章・メール・チャット・動画などのデータを横断的に取り込み、ユーザー別のコンテキストを長期記憶する「Supermemory」。これまでのAIの課題を解決するアプローチに注目が高まっています。
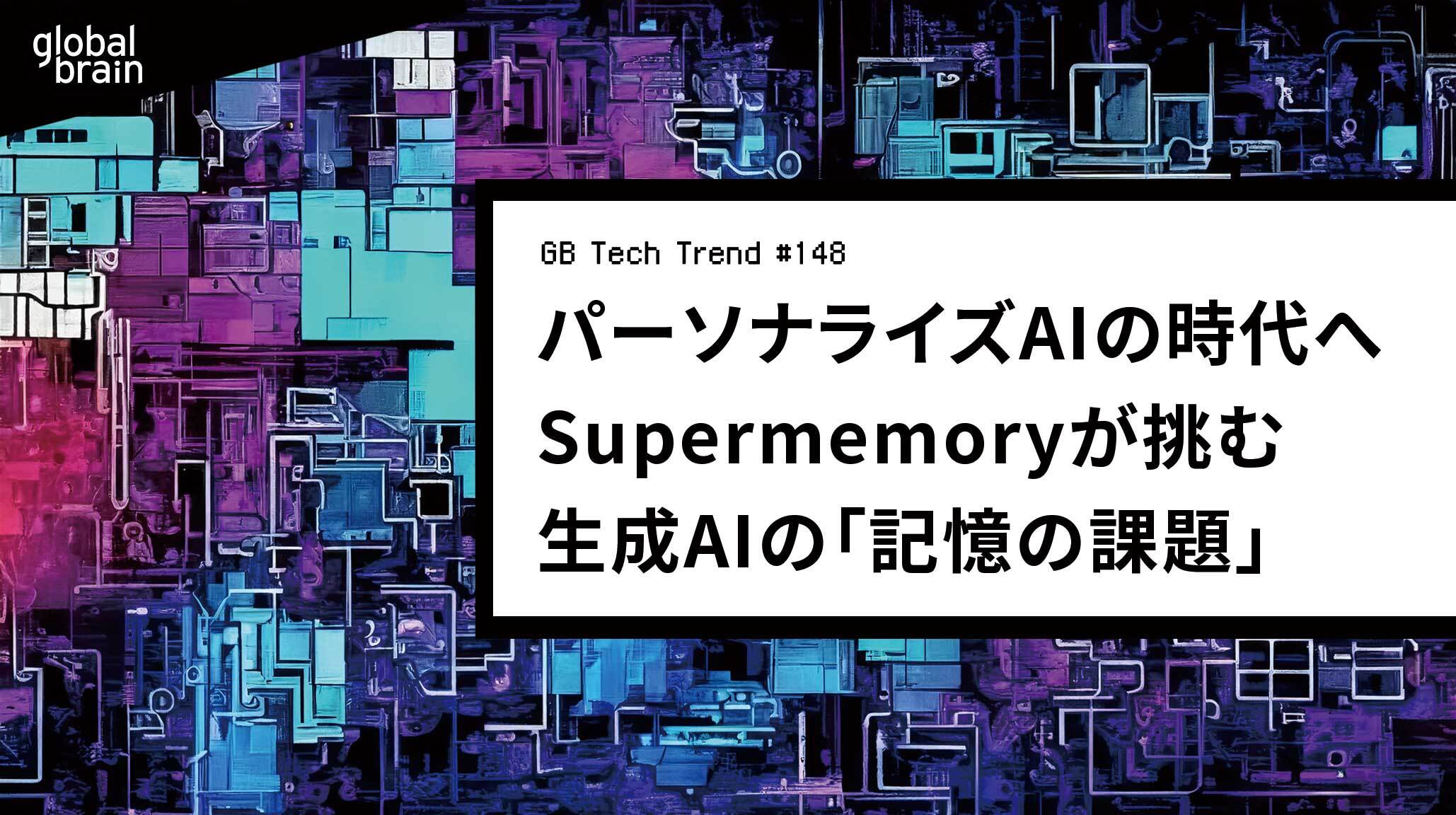
今週の注目テックトレンド
GB Tech Trendでは世界で話題になったテック・スタートアップへの投資事例を紹介します。

ChatGPTの登場以降、LLMは急速に社会実装が進みましたが、初期から変わらない課題が「記憶」です。対消費者向け生成AIサービスは、短期記憶を指す「コンテキストウィンドウ」を前提とし、セッション単位で一時的にテキストを読み込んで、応答を最適化するアプローチが主流です。
しかし、セッションを切り替えれば直前までの会話は失われ、過去の指示や背景を毎回貼り直す必要が生じます。そういった背景情報が増えるたびにプロンプトは長文化し、計算コストも応答遅延も増えてしまいます。この非効率性はユーザー体験の課題として積み上がってきました。
ユーザー別にコンテキストを記憶する
こうした前提を改善するのが長期記憶モデルです。今回紹介する「Supermemory」は、まさにこのセッション横断の記憶レイヤーを提供するスタートアップです。創業者は19歳のDhravya Shah氏。直近では260万ドルの資金調達が報じられています。
Supermemoryは、ファイル・文章・メール・チャット・動画といったデータを横断的に取り込み、ユーザー別のコンテキストを長期記憶として構築します。あらゆるコンテキストから必要最小限の情報を、必要なときに取り出す設計であるのが特徴です。これにより、プロンプトの肥大化を抑えつつ、過去の意図や依頼履歴を踏まえた一貫した応答を実現します。同社ではAPIとして長期記憶モデルを提供しており、これを「ユニバーサルメモリーAPI」と称しています。
「パーソナライズAI」の時代へ
長期記憶の基礎技術としては「知識グラフ」と「ベクトル検索」が代表的です。
知識グラフは、ユーザーが残した人や出来事に関する事象を点として表し、それらを線で結んで関係性をグラフにして整理する仕組みです。一方、ベクトル検索では言葉の意味を数値で表し、その距離が遠いか近いかによって関連する要素を高速で引き当てます。Googleでは十年以上前から前者の知識グラフを運用して精度向上に取り組んできました。
長期記憶レイヤーが目指すのは、個人単位でその人の「ブレインマップ」のようなグラフを構築することです。Supermemoryではこの考え方をもとに、抽出・要約・正規化の前処理を記憶側に寄せ、推論時には必要断片だけを低遅延で供給するアプローチを打ち出しています。
短期記憶しかないAIの世界では、スレッドや並行チャットの間の橋渡しができず、同じ説明を繰り返したり、資料の所在を再検索したりといった手戻りが発生していました。Supermemoryのような長期記憶レイヤーを活用すれば、セッションを横断しても整合性の取れたAI回答が可能になり、参照する情報も一貫性を保てます。
開発者側は巨大なプロンプト設計の手間から解放され、ユーザー側はパーソナライズされたコンテキストを共有したまま別セッションに移動できるわけです。つまり、誰もが「パーソナライズAI」を持てる時代へと一歩前進できます。この時代では、たとえばAIチャットボットだけでなく生活ロボットのような存在がユーザーの個別習慣を学習しやすくなります。生成AIがコミュニケーションや家事手伝いの領域にまで普及する可能性が高まっていくと言えるでしょう。
長期記憶スタートアップの未来
長期記憶分野にはすでに複数のプレイヤーが参入しています。
「Mem0」はその1社で、AIアプリ向けのメモリーレイヤーを掲げるY Combinator発のスタートアップです。資金面でも約2,400万ドルの累計調達を行っています。
「Letta」も競合として挙げられます。2024年に1,000万ドルの資金調達を公表し、「スリープタイム・コンピュート」を提唱しているのが特徴です。これはユーザーが使っていない待機時間に、エージェントが記憶を書き換えて編成するというアプローチのことで、これにより推論の瞬間の負荷を軽くしながら回答の一貫性と鮮度を高めることができます。メインエージェントとスリープタイムエージェントの並列体制で長期記憶を更新しているわけです。
こうした長期記憶レイヤーのスタートアップにとっては、ローカルLLMの普及が追い風になります。オンデバイスや社内サーバで完結するローカルLLMでは、即時応答が求められるためパフォーマンスの高い記憶モデルが必要とされるからです。
そこで「重い前処理は非同期で行い、推論時は必要最小限の情報を取り出す」という長期記憶の価値が一段と高まります。AppleやGoogle、MicrosoftなどがオンデバイスでのAI強化を進めるほど、記憶レイヤーサービスの買収・内製化は十分に起こりうるシナリオです。発話履歴や参照権限を跨いだ「記憶の管理」は大手IT企業が最も重視する論点であり、そこをクリアできるプレイヤーはプラットフォーム統合のために必要とされるでしょう。
10月7日〜10月20日の主要ニュース

スマートリング「ŌURA」、約110億ドル評価で9億ドル調達
健康管理向けのスマートリングを展開する「ŌURA」は、Fidelityがリードを務め、ICONIQに加えて既存投資家のWhale RockとAtreidesも参加するラウンドで9億ドルを調達、約110億ドルの評価額に到達した。サンフランシスコとフィンランドを拠点にする同社は、設立12年目を迎える。
同社は累計550万個超のスマートリングを販売し、その半数以上を過去1年で達成。2024年の売上は5億ドルと前年から2倍に伸長し、今年は売上10億ドル超を見込む。IDCの昨年のレポートでは、スマートリング市場で80%超のシェアを握るとされる。— 参考記事
900万回超の自動配送「Starship」が米都市へ本格展開
自律走行のデリバリーロボットを開発・運用する「Starship Technologies」は、Pluralがリードし、Karma.vc、Latitude、Coefficient Capital、SmartCap、Skaalaが参加するシリーズCラウンドで5,000万ドルを調達。累計調達は2.8億ドル超となった。
同社は900万回超の自律配送(米国競合合計の5倍)と1,200万マイル超の走行を達成。2,700台超の保有ロボ隊を2027年までに1.2万台超へ増強し、欧州30都市と米国60以上の大学キャンパスでの成功をもとに、米国の都市部で本格スケールを図る。欧州での運用ではCO₂排出を650トン以上削減するゼロエミッション配送を実現している。— 参考記事
ゲーム動画で空間推論を学習「General Intuition」が1.34億ドル調達
ビデオゲーム映像を用いてAIエージェントに動きや空間理解を学習させる「General Intuition」は、Khosla VenturesとGeneral Catalystが共同でリードし、Raineも参加するシードラウンドで1億3,370万ドルを調達した。
同社は、Medalが持つ月間アクティブ1,000万人、年間20億本規模のゲーム動画データを活用。数万タイトルにおよぶ多様なゲームソースは、TwitchやYouTubeの代替を超える訓練素材になり得ると見込む。— 参考記事
オンライン個人金融「Upgrade」、シリーズGラウンドで1.65億ドル調達
オンラインの個人向けローンやクレジットカード、モバイルバンキングを提供する「Upgrade」は、Neuberger Bermanがリードし、LuminArx Capital Managementのほか既存投資家のDST GlobalとRibbit Capitalも参加するシリーズGラウンドで1億6,500万ドルを調達。ポストマネー評価額は73億ドル超、累計調達は7.5億ドルに達した。
同社は当初小口パーソナルローンからスタートし、当座・貯蓄口座、クレジットカード、信用スコア管理、BNPLまで拡充。2023年には旅行向けBNPL(Buy Now, Pay Later)のUpliftを1億ドルで買収した。前回資金調達以降で売上は2倍超となり、5月には年換算売上が10億ドルを突破したという。— 参考記事
(執筆:GB Brand Communication Team)