創業6カ月で買収額8,000万ドル──「Base44」に見るバイブコーディング最前線【GB Tech Trend #142】
自然言語のプロンプトで入力するだけで、AIが自動的に構築してくれる新たな開発手法「バイブコーディング」。このバイブコーディングによって誕生した企業例や、スタートアップエコシステムへの影響について考察します。
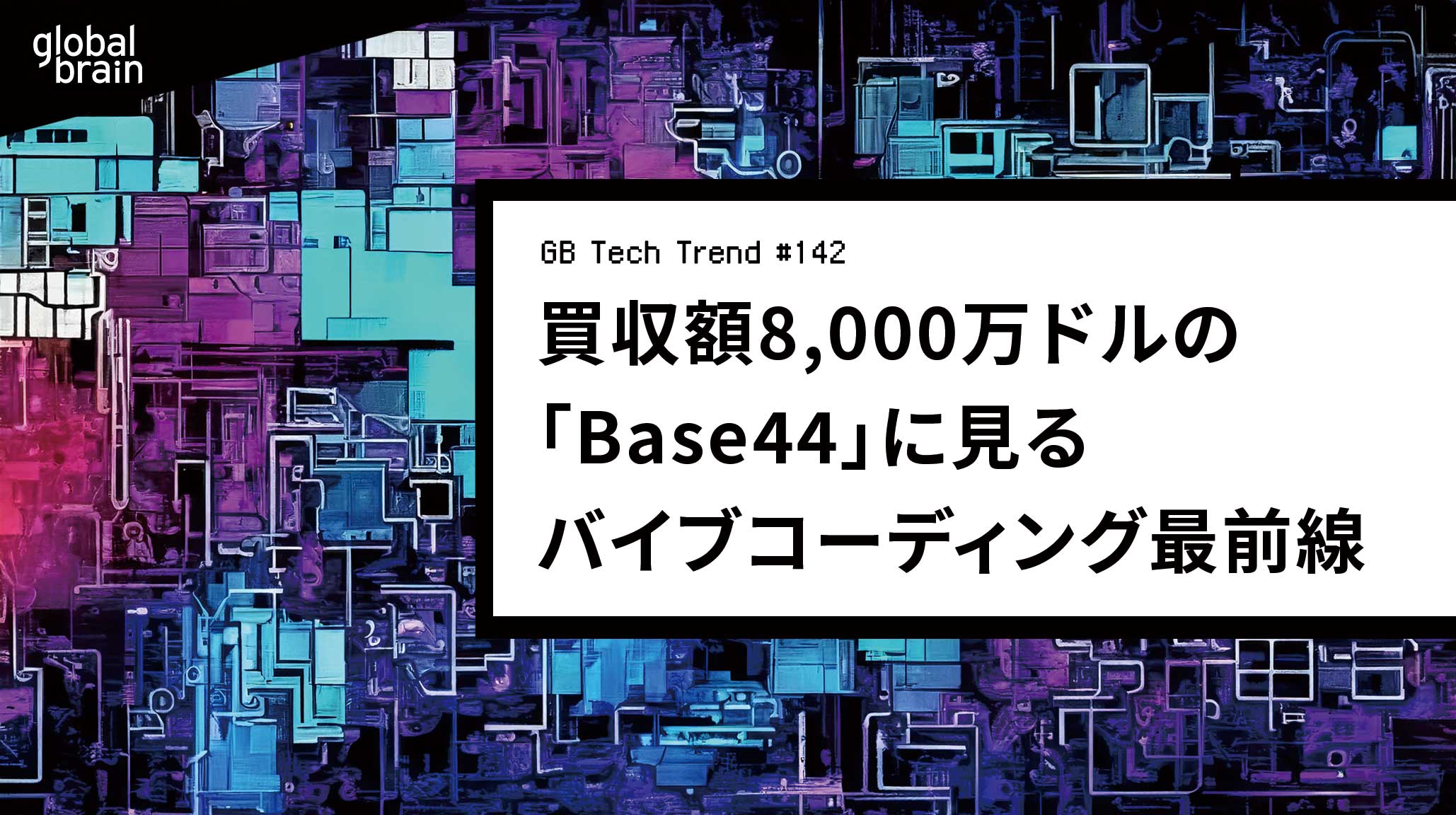
今週の注目テックトレンド
GB Tech Trendでは世界で話題になったテック・スタートアップへの投資事例を紹介します。
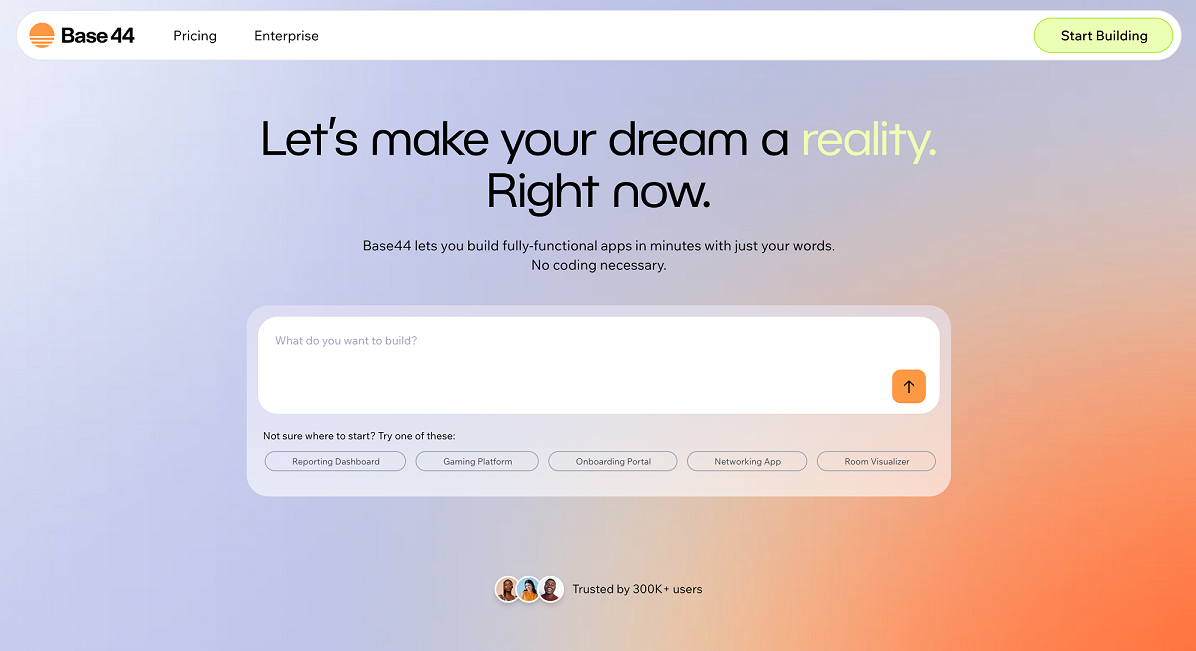
ユーザーが求めている機能を、自然言語のプロンプトで入力するだけでAIが自動的に構築してくれる「バイブコーディング」。OpenAI創業メンバーのAndrej Karpathy氏が提唱したこの概念が急速に普及し、アプリ開発のあり方を根底から変えつつあります。プロダクトの立ち上げから黒字化、さらにはエグジットまでのサイクルが圧倒的なスピードで進行するようになったことで、個人開発者のプロダクトのあり方からスタートアップの経営戦略に至るまで、開発をめぐる前提が大きく塗り替えられてきている状況です。
急拡大する「バイブコーディング起業」
この最前線にいるのが、創業からわずか6カ月でWebサイトビルダー大手「Wix」に約8,000万ドルで買収されたスタートアップ「Base44」です。同社は一切資金調達を行っていないブートストラップで成長を遂げたスタートアップであり、Base44自体がバイブコーディングを駆使して立ち上げられたプロダクトです。まさにバイブコーディングのトレンドを象徴する存在と言えるでしょう。
Base44の最大の特徴は、プロンプトを入力するだけで、データベース・認証・ストレージ・分析・外部API統合を含むフルスタックアプリケーションを自動生成できる点です。
一般的な競合はフロントエンドの生成に特化し、バックエンドはSupabaseなどの外部サービスに依存する構成が多いなか、Base44はフロントからバックエンドまで一貫した構成を実現。この統合性が、実務レベルで使えるプロダクトの迅速な開発を可能にしています。
創業者Maor Shlomo氏は、自身のLinkedIn投稿で、2025年5月時点での純利益が18.9万ドルに達していることを明かしています。LLMのトークンコストを差し引いた後でも黒字化を果たしており、その事業性は数字のうえでも明確です。さらに、リリースから3週間で1万ユーザーを獲得、買収時点では25万ユーザーを抱えていたことからも、プロダクトに対する強い市場ニーズがうかがえます。YouTube上のインタビューでは、ARR100万ドルに3週間で到達していたことも語られており、その急成長ぶりは注目に値します。
Base44の成功は特異な例ではなく、バイブコーディング市場そのものがいま、急速に拡大しています。その代表的なプレイヤーが「Lovable」です。Financial Timesの報道によれば、Lovableは2億ドルの企業評価額を目指して1.5億ドルの資金調達に動いており、創業からわずか半年でARR5,000万ドルを達成しています。スピード感で言えば、Base44をも凌ぐ勢いです。
Lovableは比較的小規模なチームで開発が進められてきましたが、Base44も買収の1.5か月前まで、ほぼ創業者1人で運営されていたことが語られています。これはOpenAIのSam Altman氏が提唱する、AIとともに1人で巨大企業を築くという考え方「1人ユニコーン」とはやや異なりますが、数人でプロダクトを磨き上げ、短期間で黒字化を達成するというバイブコーディング界隈ならではのアプローチは、まさにトレンドと言えるでしょう。
ソロプレナーが変えるスタートアップ構造
バイブコーディングによって開発のハードルが大きく下がったことで、従来のように大規模なチームを組んで起業するのではなく、1人でプロダクトを立ち上げる「ソロプレナー(1人起業家)」の活躍が広がりつつあります。
プログラマーが単独でアプリを開発・リリースし、継続的な収益を得るスタイルは当然これまでもありました。個人開発者である彼らは「インディーメーカー」と呼ばれ、代表的な人物にはJon Yongfook氏(MRR7万ドル超)や、levelsio氏(MRR13万ドル超)などが挙げられます。
一方、バイブコーディングによって生まれてきたソロプレナーは、単に個人で小さなプロダクトをつくるインディーメーカーとは異なり、数千万円〜数億円規模のエグジットや、黒字化による長期運営を視野に入れる「事業性のある個人起業家」を指します。1,000億円規模の企業価値やIPOを前提とした、いわゆる「ホームラン型」のスタートアップとは一線を画す新しい起業のスタイルです。
このソロプレナーの潮流をいち早く捉えて脚光を浴びているのが、AIスタートアップスタジオ「Audos」です。同社は、小規模なビジネスを立ち上げたい人を対処に、AIエージェントを活用してプロダクト開発を支援しながら、2.5万ドルの資金提供も行っています。注目すべきは、株式を取得せずに支援企業の売上の一部(15%)を継続的に得るという、従来のVCとは異なる「収益志向型」の仕組みです。
この仕組みは、たとえ1社あたりの売上が小さくとも、支援企業数を圧倒的に増やすことでポートフォリオ全体のリターンを最大化できるという発想のもと成り立っています。Audosはこのモデルを用いて年間10万社の立ち上げを目指しているとのことです。巨大な1社を生むのではなく、小さな黒字企業を大量に生み出すこの戦略は、まさに「スモールカンパニー × 連続的成功」というAI時代ならではのスタートアップ投資トレンドを象徴していると言えるでしょう。
このようにバイブコーディングの誕生は、単なる開発手法の進化にとどまらず、個人のキャリア形成、スタートアップの経営モデル、そして投資ファンドのあり方にまで波及している状況です。中小規模のプロダクトで収益を得る個人やスモールスタートアップの登場は、今後の市場構造を大きく塗り替えていく可能性を秘めています。
6月24日〜7月7日の主要ニュース
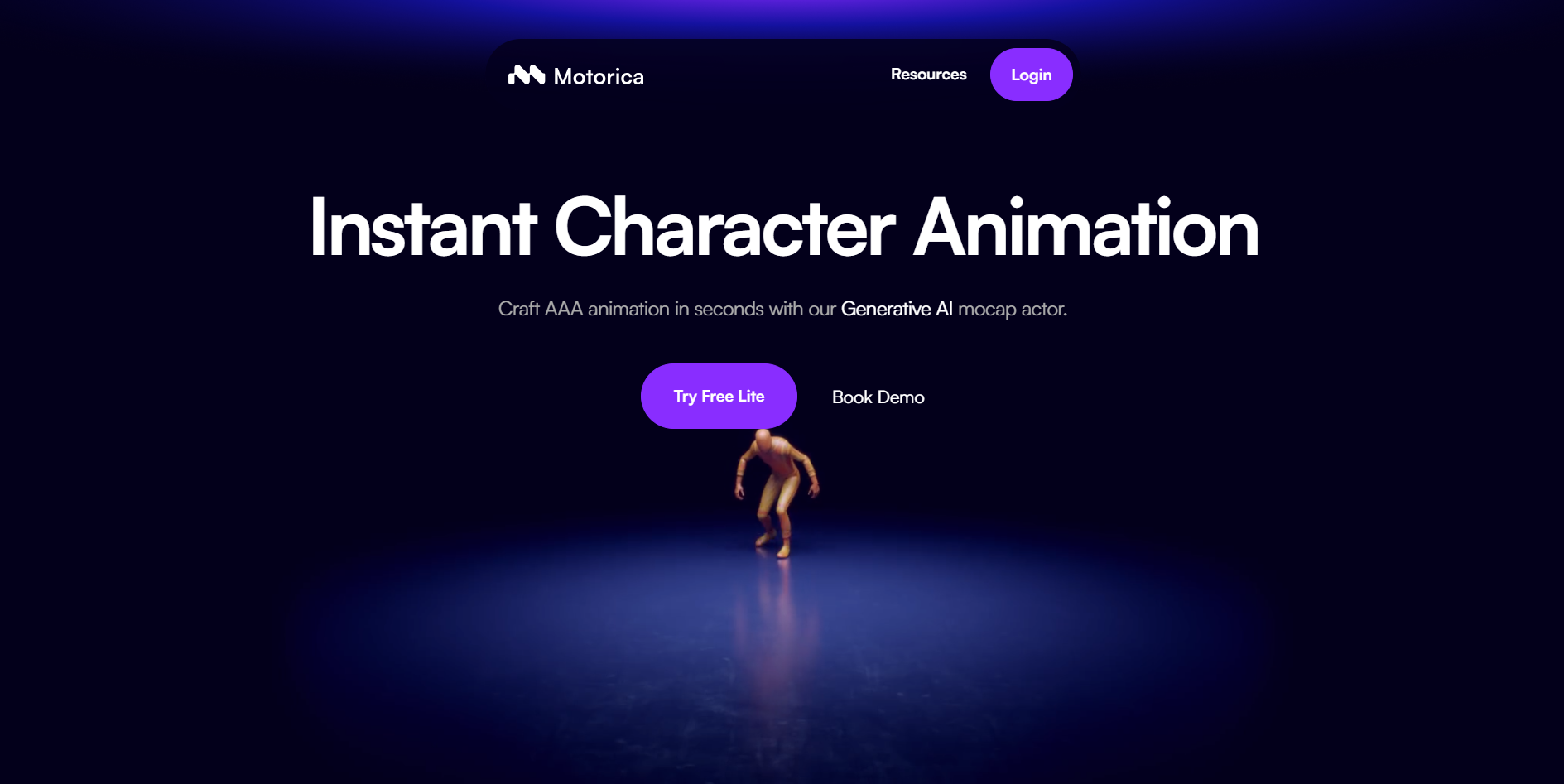
制作コスト90%減の衝撃、「Motorica」580万ドル調達
アニメやゲームスタジオが従来のモーションキャプチャーを使わずにリアルなキャラクターの動きを作成できるAIツールを開発する「Motorica」は、Angular Venturesがリードを務め、Luminar Venturesらも出資したシードラウンドで580万ドルを調達した。
Motoricaはモーション・シンセシスと呼ぶ、何千時間にも及ぶ独自のモーションキャプチャーを基に学習させたトランスフォーマーベースのAIモデルにより、忠実度の高いキャラクター・アニメーションを大規模に生成できるようにしている。同社によると、このプラットフォームを使用しているスタジオは、従来よりもアニメーションワークフローが最大200倍高速化し、90%を超えるコスト削減を実現しているという。 — 参考記事
恋の相性はAIが決める、「Sitch」が500万ドル調達
AIを活用したグループマッチングを通じて恋愛相手を見つける手助けをする「Sitch」は、M13がリードを務めたシードラウンドで500万ドルを調達した。本ラウンドにはAndreessen Horowitzも参加した。
ユーザーは約50の質問に回答した後、AIがマッチング候補を表示する。双方のユーザーがマッチングに同意すると、AIとのグループチャットに追加する。同社は75以上のマッチメイキング用のパラメータを使ってAIモデルを訓練しているという。同社はセットアップ(マッチング)ごとにユーザーに課金し、セットアップ3パック(89.99ドル)、5パック(124.99ドル)、8パック(159.99ドル)で販売している。— 参考記事
“眠っているデバイス”を活用する「Datagram」が400万ドル調達
企業がデバイス間で未使用のコンピューティング、ストレージ、帯域幅を利用できるようにするブロックチェーンを搭載したネットワークを運営する「Datagram」は、Blizzard the Avalanche Fundがリードを務めたプレシードラウンドで400万ドルを調達した。Animoca Brands、Cointelegraph、Amber Group、Aquanow、Arche Fund、DePIN X Capital、ISKRA、JDI Ventures、Yellow Capitalらも本ラウンドに参加した。
個人および企業システム全体の帯域幅、CPU、ストレージの最大80%が遊休状態にあり、ネットワーク容量の60%は十分に活用されていないという。Datagramは、こうしたアイドル状態のコンピュート、ストレージ、帯域幅を、ゲーム、AI、通信などのアプリケーション向けに電力を供給するための分散型インフラストラクチャを開発。Datagramのネットワークは、Avalancheエコシステムにいる200以上の企業パートナーと世界中の100万人以上のユーザーに対してサービス提供を目指している。— 参考記事
専門家の知見を24時間運用、「Remark」1,600万ドル調達
リテール業者向けにAIチャットボットを提供する「Remark」は、Inspired Capitalがリードを務めたシリーズAラウンドで1,600万ドルを調達した。Stripe、Neo、Spero Ventures、Shine Capital、Visible Venturesらも本ラウンドに参加した。同社は総額2,700万ドルを調達している。
Remarkは何千人もの人間の専門家に、ユーザーが商品を購入している間にチャットさせ、そのやり取りをAIの学習モデルとして利用。AIペルソナを開発することで、実際の専門家がいなくとも24時間対応可能な専門家チャットボットサービスを提供。同社はパートナーの純収入が10%増加したと述べている。— 参考記事
(執筆: Universe編集部)