料理動画メディア「Tastemade」買収の裏側──フード市場の「スーパーアプリ」を目指すWonder【GB Tech Trend #135】
これまでも複数の企業を買収してきたWonder。「レシピ」「配達」「メディア」の3つを強化しようとしている同社の戦略を考察しました。
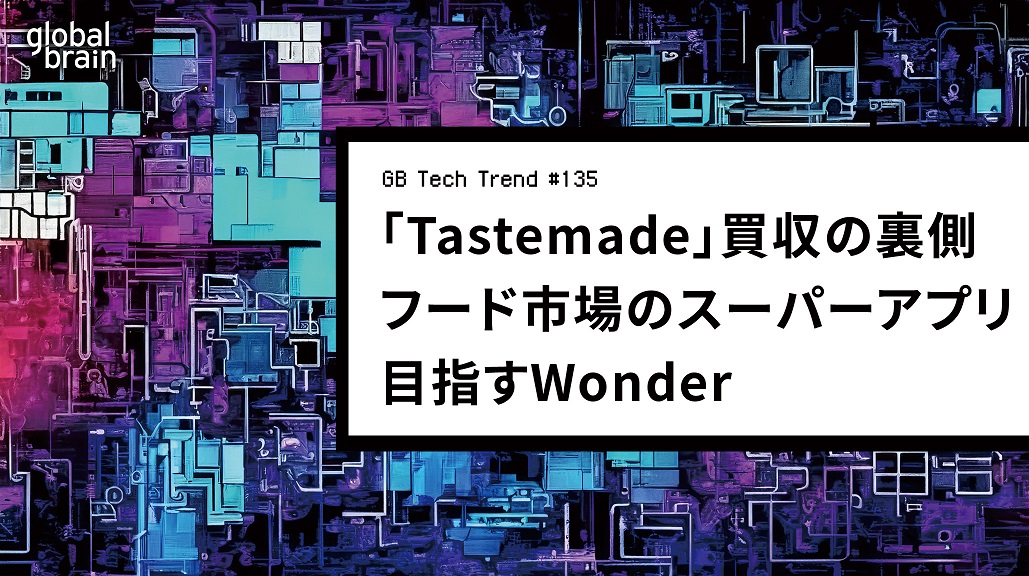
執筆: Universe編集部
今週の注目テックトレンド
GB Tech Trendでは世界で話題になったテック・スタートアップへの投資事例を紹介します。

累計16億ドルの資金調達を実施しているフード配達企業「Wonder」が料理動画メディア「Tastemade」の買収を発表しました。買収額は9,000万ドルと、スタートアップ買収としては大型案件となっています。
Tastemadeは2012年に創業され、動画メディアが乱立した2015年前後の時代から生き残ってきた大手メディアスタートアップです。料理だけでなく、旅行やホーム領域などをテーマに、さまざまな番組を放映するストリーミングチャンネルも運営し、従来のTV番組に取って代わる市場ポジションを確立しています。
現在は有料プラン「Tastemade +」を展開しつつ、年間9,300万ドルの売上を立てているとされている同社。日本の「クラシル」のような料理レシピへのアクセス権や、会員限定番組をグローバル規模で展開し、動画メディアとして成功モデルを築いています。
これまでも進んでいた、Wonderの買収戦略
対するWonderは2018年の創業以来、急成長を遂げているフード配達スタートアップです。著名なシェフの料理を楽しめるレストランを全米30店舗超運営しており、アプリから注文すると10分以内に配達してくれます。各店舗はイートインも可能ですが、基本的にはフード配達向けの調理拠点という位置づけです。
店舗では1人のシェフの料理だけではなく、最大30以上のフードブランドの料理を楽しめる「料理ブランドのハブ」になっています。どんな料理もすぐにデリバリーできる厨房を備えた、いわゆる「ゴーストキッチン」の機能を強く意識した店舗運営となっているのが特徴です。
一見、「フード配達」と「料理メディア」は市場が異なるように感じますが、今回の買収劇の背景には、Wonderが目指す「スーパーアプリ企業」としてのビジョンが挙げられます。このビジョン達成のために、Wonderは「レシピ」「配達」「メディア」の3つを強化してきており、そのためにこれまでにも3社の買収を行ってきました。
最初にWonderが買収したのは、多くのシェフと提携し、豊富なレシピ数を持つミールキットスタートアップ「Blueapron」です。著名シェフとの提携数を増やし、レシピ数と各店舗で取り扱うフードブランド数を最大化させることが目的だったと考えられます。また、WonderはUberEatsとDoorDashに次ぐ全米第3位のフード配達企業「Grubhub」も買収し、配達ネットワークの強化にも取り組みました。
この2社の買収によって、シェフに共有してもらったレシピを、調理から配達までを自社で一気通貫に行い、顧客の元まで料理を届けるロジスティクスを構築してきたのが現在のWonderです。そして今回「Tastemade」を買収することで、Wonderが提供できる料理をなるべく多くの顧客に想起してもらえるメディア機能を保有するに至りました。
Tastemadeによってスーパーアプリ化が加速
UberEatsやDoorDashなどの台頭により、フード配達市場はレッドオーシャン化とコモディティ化が進み、サービスの差別化がますます難しくなってきています。こうした競合環境の中では、顧客の生活シーンにいち早くリーチし、Wonderで提供できる料理を想起してもらう必要があります。
そこでWonderは、月間3億視聴を誇るフードメディア大手のTastemadeを買収しました。他社には真似できない料理を、Tastemadeを通じて世界中に拡散してもらい、強力なサービス成長を目指せる体制を確立しようとしたと言えます。
Tastemadeを傘下に持つと、外部広告に依存する必要がなくなるのでCAC(Customer Acquisition Cost)削減にもつながります。長期的に考えると、Wonder本体事業であるフード配達やミールキット部門の収益を向上させることにつながり、盤石な成長基盤を築くことができるでしょう。
世界中どこにいてもTastemadeの動画で美味しい料理を知ることができ、それを即座に注文することで10分以内に料理が届く体験は、まさに「スーパーアプリ企業」としてのWonderが目指すところです。今回Tastemadeを買収したことで、川上から川下までを抑えた一大料理バリューチェーンの構築という、スーパーアプリビジョンの達成に一歩近づいたと言えるのではないでしょうか。
3月11日〜3月24日の主要ニュース
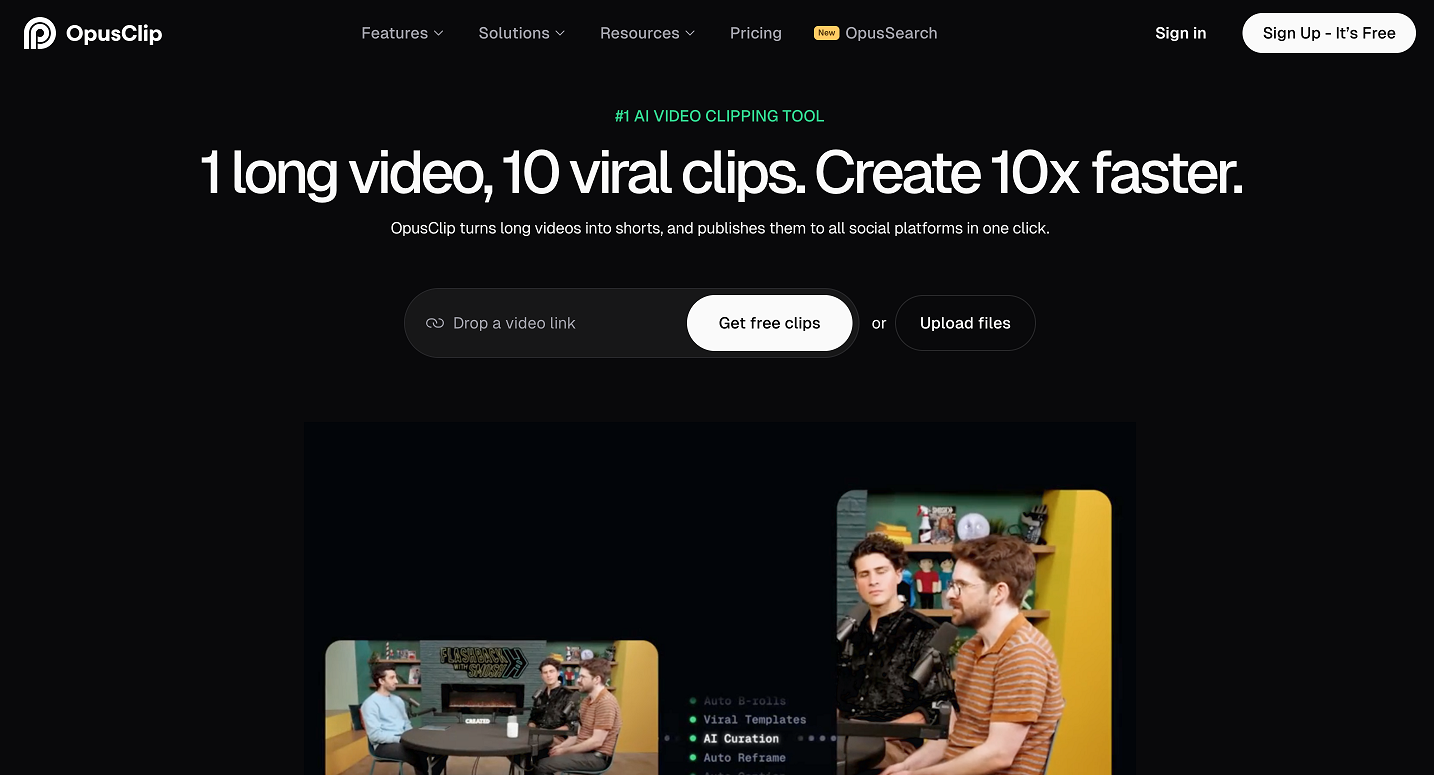
570億回再生したAI動画編集プラットフォーム「OpusClip」、SoftBankらから2,000万ドル調達
長編動画をソーシャルメディアに適した短く魅力的なクリップに変換するよう設計されたAI動画編集プラットフォーム「OpusClip」は、SoftBank Vision Fund 2がリードし、DCM Ventures、AIGrant、Millennium New Horizonsが参加するラウンドで2,000万ドルを調達した。
1,000万人のユーザーが1億7,200万以上のビデオクリップを作成し、その総再生回数は570億回に達している。サービスローンチからわずか1年ほどで、すでにARRは数千万ドルを達成しており、急速にユニコーン企業の道を歩んでいるという。— 参考記事
AI画像生成のライセンスチェックで急成長中の「Bria」が6,500万ドル調達
すべてのコンテンツが合法的にライセンスされていることを確認しながら画像を生成できる「Bria」は、Red Dot Capitalがリードを務め、Maor Investment、Entrée Capital、GFT Ventures、Intel Capital、IN Ventureらが出資するシリーズBラウンドで4,000万ドルを調達した。同社は総額約6,500万ドルを調達している。
BriaはGetty Imagesを含む約20のパートナーから画像を購入し、画像生成モデルを訓練している。ライセンスを持つ画像が生成画像に使われる場合は、自動的にライセンス所有者に使用料が支払われる。現在、Briaは40の顧客を抱えており、昨年は年間売上が400%以上の大幅な伸びを示した。今後は年末までにチーム規模を倍増させる予定だという。— 参考記事
AIで回収コストを50%削減する「ClearGrid」が650万ドル調達
銀行、フィンテック、貸金業者向けの債権回収プロセスを自動化するAIプラットフォーム「ClearGrid」は、Raed VenturesとNuwa Capitalの共同でリードしたシードラウンドで650万ドルを調達した。Beco Capital、Waed Ventures、KBW Ventures、Sharakaも出資した。同社は総額1,000万ドルを調達している。
ClearGridのプラットフォームは、支払い能力と支払い意欲に基づいて債務者を分類し、返済を管理可能な小額に分割、強制することなく返済に向かわせる。このプラットフォームによって回収コストを50%削減できるとのこと。また、同社プロセスの95%は完全に自動化されており、その中には毎日何十万件もの電話に対応するAI音声エージェントも含まれている。— 参考記事
貨物輸送の非効率を解消する「Augment」が2,500万ドルを調達
電子メール、電話、ワークフローの管理などの複雑なタスクを扱う貨物輸送オペレーターを支援するAIアシスタントを開発する「Augment」は、シードラウンドで2500万ドルを調達した。8VCがディールリードを務めた。
9,000億ドル規模の貨物輸送産業では、90万のトラック運送会社と2万社以上のブローカーが、電子メール、電話、データ入力、書類転送といった手作業によるコミュニケーションに頼って出荷を調整しているため、運送会社とブローカーは低い利益率を強いられている。この問題解決に取り組むのがAugmentである。— 参考記事
ペット6万匹が加入するヨーロッパの保険スタートアップ「Dalma」が2,180万ドル調達
フランスとドイツで犬と猫の健康保険を提供する「Dalma」は、BreegaがリードするシリーズBラウンドで2,180万ドルを調達した。Bpifrance Digital Venture 3とNorthzone、Anterra Capitalもラウンドに参加した。
現在、Dalmaには保険に加入しているペットが6万匹いるとのこと。また、シリーズA以来700%の成長を遂げ、フランスではすでに黒字を達成しており、ペット保険業界の重要なプレーヤーとしての市場ポジションを確立するのに十分な位置にあるという。— 参考記事